 ロックと政治が結びつくことにどうしようもなく違和感を感じる。アメリカだけでなく世界中のアーティストがオバマを支持しようとも、僕は言いようのない居心地の悪さを感じる。オバマとがっちり握手をしているブルースの姿を見たときもそうだった。
ロックと政治が結びつくことにどうしようもなく違和感を感じる。アメリカだけでなく世界中のアーティストがオバマを支持しようとも、僕は言いようのない居心地の悪さを感じる。オバマとがっちり握手をしているブルースの姿を見たときもそうだった。
なのに、僕はこのアルバムを聴いてすごく感動してしまった。感動と言うよりはドキドキしてしまった。ロックを聴いてドキドキしたのは久しぶりのことかもしれない。ワクワクすることはよくある。でも、ドキドキは本当に久しぶりだと思う。政治的背景や思想からは切り離せないのだろうが、僕自身は全くそれを抜きにしてこのアルバムを楽しんでいる。
昔Born To
Runが好きで、小学生の頃友達にレコードをテープに録音してもらって、本当によく聴いた。何度も何度も聴いた。Thunder
RoadからJungle
Landまで全く無駄のない、まさに奇跡のようなアルバムだと思っていた。素晴らしいロックンロールを聴くと、胸がドキドキした。Born To
Runはそんな1枚なのである。
30年以上前にリリースされたそのBorn To
Runとこのアルバムを比べるわけではないのだが、あの頃と同じようなドキドキを今作では感じることができる。ポップでメロディアスでわかりやすいロックン・ロールアルバム。風のような疾走感にあふれ、抜けの良い楽曲が並ぶ。
前作Magicもブルース本来のメロディーセンスが解放されたアルバムであったが、今作では更に解放され、様々なタイプの楽曲に挑戦している。盟友E
Street
Bandとの抜群のコンビネーション、ストリングスやオルガンを上手く使いながら、ポップでドリーミーなテイストを演出するなど冒険的な要素もある。でも、ボス・クラシックとも言うべきロックンロールナンバーの切れの良さが実に素晴らしい。
また、メッセージもこれほどわかりやすい言葉でメッセージを伝えようとするブルースも久しいのではないだろうか。Working On A
Dreamでは「夢を追い続けている」「いつの日か 夢を叶えてくれるはず」と何度も歌われる。かなり恥ずかしく思われるかもしれない。しかし、40年以上ステージに立ち、その瞬間を「奇跡」と称するブルースは誰がなんと言おうとも本気でそう思っているのだろう。そういう強さが、メロディーからサウンドからビシバシ伝わってくるのだ。言葉を支える強靱な音と歌がそこにはある。
思えばいつからかブルースは僕から遠いところへ行ってしまった。小難しいところはあったが、終始小難しい顔をしてアメリカの苦悩を歌う彼に一日本人が共感するのはとても難しいことだと思う。そんな年月が続いたが、ブルースは戻ってきた。50代後半になってもこれだけポジティブで力強いメロディーが湧き上がってくるとは、正直思っていなかった。これもまた、「奇跡」の瞬間なのかもしれない。
おすすめ度★★★★★(08/02/09)
 「酔いどれ詩人」「ベッドルームシンガー」などと語られることの多い彼の今作は、ニック・ホーンビィ(大好きである)の小説の映画のサウンドトラックである。デビュー作「The
Hour Of Bewilder
Beast」は、甘いメロディーをアイディア豊富なやり方で聴かせてくれた。もちろん大好きな曲もたくさんあるが、時折もっとストレートなアプローチで聴かせてほしいと思うこともあった。
「酔いどれ詩人」「ベッドルームシンガー」などと語られることの多い彼の今作は、ニック・ホーンビィ(大好きである)の小説の映画のサウンドトラックである。デビュー作「The
Hour Of Bewilder
Beast」は、甘いメロディーをアイディア豊富なやり方で聴かせてくれた。もちろん大好きな曲もたくさんあるが、時折もっとストレートなアプローチで聴かせてほしいと思うこともあった。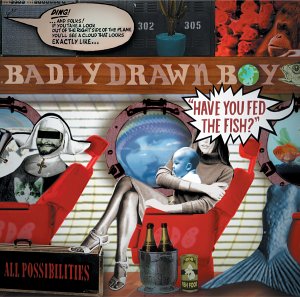 前作「About A
Boy」でスタンダードもガンガンいけるという力量をいかんなく発揮したデーモン・ゴフ。この新作では、彼本来の奇天烈さを醸し出したポップソングが聴けるのかと思ったが、意外とストレートに、ふつうにいい曲満載のアルバムとなった。「About〜」では、映画のサントラであるという制約がいい方向に生きた、という風に押さえていたが、彼本来のスタイルとは違っていて、きっと次の作品では一筋縄行かない、おもちゃ箱ポップスが待っているのだと僕は強く確信していた。しかしながら、本作は大きくシフトチェンジされたものではなく、わりかし素直にメロディーを鳴らしている。はっきり言えば「About〜」と前々作「The
Hour Of Bewilder
Beast」の中間作。だから演奏と楽曲のバランスはすごくよくとれている。
前作「About A
Boy」でスタンダードもガンガンいけるという力量をいかんなく発揮したデーモン・ゴフ。この新作では、彼本来の奇天烈さを醸し出したポップソングが聴けるのかと思ったが、意外とストレートに、ふつうにいい曲満載のアルバムとなった。「About〜」では、映画のサントラであるという制約がいい方向に生きた、という風に押さえていたが、彼本来のスタイルとは違っていて、きっと次の作品では一筋縄行かない、おもちゃ箱ポップスが待っているのだと僕は強く確信していた。しかしながら、本作は大きくシフトチェンジされたものではなく、わりかし素直にメロディーを鳴らしている。はっきり言えば「About〜」と前々作「The
Hour Of Bewilder
Beast」の中間作。だから演奏と楽曲のバランスはすごくよくとれている。 正直言うとこのアルバムのどこが「わかりにくい」のかが分からない。「メロディーにフックがない」という意見は分からないでもないが、デーモンの場合そのフックが強過ぎる部分もあるので、僕としては今作のように若干抑えめの方がちょうどいいくらいである。前々作「About
A
Boy」はまさに映画のサントラというある種の「制約」が逆に彼のポップネスを全開とさせるいい効果をもたらしたアルバムで、今もよく聴くくらい好きな作品である。前作「恋を見ていた少年」は逆にポップネスを追求しているのか、それとも複雑なサウンドプロダクションを主としたいのかイマイチよく分からなかった。デーモンの努力の跡はすごく伺えるのだけど、かえってくどさを僕は感じた。
正直言うとこのアルバムのどこが「わかりにくい」のかが分からない。「メロディーにフックがない」という意見は分からないでもないが、デーモンの場合そのフックが強過ぎる部分もあるので、僕としては今作のように若干抑えめの方がちょうどいいくらいである。前々作「About
A
Boy」はまさに映画のサントラというある種の「制約」が逆に彼のポップネスを全開とさせるいい効果をもたらしたアルバムで、今もよく聴くくらい好きな作品である。前作「恋を見ていた少年」は逆にポップネスを追求しているのか、それとも複雑なサウンドプロダクションを主としたいのかイマイチよく分からなかった。デーモンの努力の跡はすごく伺えるのだけど、かえってくどさを僕は感じた。
 以前から噂されていた、ブライアン選曲のベスト盤。かの名盤「Petsounds」が本国アメリカで振るわなかったのは有名であるが、実はイギリスでは高く評価され、「Petsounds」はイギリス人には熱狂的に迎え入れられた。そして、「Good
Vibration」以降アメリカで下火になっていったのとは対照的にイギリスでは人気が過熱し、68年にはアーティストの人気投票でビートルズを抜くのである。なんとも、「らしい」エピソードである。ブライアンの完全無欠なポップソング、ひたすらアメリカ的であったバンドが突然奏でた「Not
American」な音、ポール・マッカートニーが受けた強いバイブが「サージェント・ペッパーズ〜」につながっていったように、この音を受け入れる素養はイギリスにしかなかったのだろう。そして、そんなところが昔の僕のUK志向につながってたように思う。
以前から噂されていた、ブライアン選曲のベスト盤。かの名盤「Petsounds」が本国アメリカで振るわなかったのは有名であるが、実はイギリスでは高く評価され、「Petsounds」はイギリス人には熱狂的に迎え入れられた。そして、「Good
Vibration」以降アメリカで下火になっていったのとは対照的にイギリスでは人気が過熱し、68年にはアーティストの人気投票でビートルズを抜くのである。なんとも、「らしい」エピソードである。ブライアンの完全無欠なポップソング、ひたすらアメリカ的であったバンドが突然奏でた「Not
American」な音、ポール・マッカートニーが受けた強いバイブが「サージェント・ペッパーズ〜」につながっていったように、この音を受け入れる素養はイギリスにしかなかったのだろう。そして、そんなところが昔の僕のUK志向につながってたように思う。 僕はBeatlesかなり好きな方である。が、世の中にはきっともっともっと熱心な方がいるのも知っている。だから、あんまりあれこれいうのもいつもおこがましいような気がしている。しかしながら、例えば同じ職場の人間が知っている洋楽のバンドといえばBeatlesとあとわずかしかいないわけで、そんな中でつい彼らの話題が出てきたら、ついつい熱く語ってしまう。
僕はBeatlesかなり好きな方である。が、世の中にはきっともっともっと熱心な方がいるのも知っている。だから、あんまりあれこれいうのもいつもおこがましいような気がしている。しかしながら、例えば同じ職場の人間が知っている洋楽のバンドといえばBeatlesとあとわずかしかいないわけで、そんな中でつい彼らの話題が出てきたら、ついつい熱く語ってしまう。 あまり話題になっていないようですが、これは素晴らしいです。ソングライターとしてのベックの力量がいかんなく発揮された作品。Ashのようなキャッチーさはないが、心にジワリジワリとしみこむメロディーにやられてしまいます。「ミューティションズ」とよく比較されますが、今回は「ミューティションズ」の時よりグッとサウンドがシェイプされ、その分楽曲の構成やメロディーが非常に伝わりやすくなっています。この手のサウンドは、楽曲そのものがそのシンプルさに耐えうる力を持っていないとただつまらないだけなのですが、さすがはベック。楽曲の完成度は今までの作品の中でも一番ではないでしょうか。アコギ中心としながら、時に押し寄せてくるストリングスやノイズが非常にスリリングな魅力を醸し出していて、この辺はやはりプロデューサーのナイジェル・ゴドリッチの十八番と言ったところでしょうか。本当に仕事のできる男です。個人的にはベックのアルバムの中で一番好きです。
あまり話題になっていないようですが、これは素晴らしいです。ソングライターとしてのベックの力量がいかんなく発揮された作品。Ashのようなキャッチーさはないが、心にジワリジワリとしみこむメロディーにやられてしまいます。「ミューティションズ」とよく比較されますが、今回は「ミューティションズ」の時よりグッとサウンドがシェイプされ、その分楽曲の構成やメロディーが非常に伝わりやすくなっています。この手のサウンドは、楽曲そのものがそのシンプルさに耐えうる力を持っていないとただつまらないだけなのですが、さすがはベック。楽曲の完成度は今までの作品の中でも一番ではないでしょうか。アコギ中心としながら、時に押し寄せてくるストリングスやノイズが非常にスリリングな魅力を醸し出していて、この辺はやはりプロデューサーのナイジェル・ゴドリッチの十八番と言ったところでしょうか。本当に仕事のできる男です。個人的にはベックのアルバムの中で一番好きです。 Beckの新作はゴリゴリのギター、重たいビートで幕を開ける。聴けばすぐに分かるように、これはやはり「オデイレイ」的なものにBeckが再び取り組んだ作品であろう。Beck個人と言うよりは後ろに「with
Dust Brothers」と加えるべきではないかと言うくらいヒップホップ、エレクトリックが上手く取り入れられ、それがBeckのメロディーとがっちり与し、2005年式のロックとしてしっかり鳴り響いている。また、1曲1曲が意外とコンパクトに出来ているが、サウンドの絡みが凄く濃厚なのでいいバランスになっていると思う。
Beckの新作はゴリゴリのギター、重たいビートで幕を開ける。聴けばすぐに分かるように、これはやはり「オデイレイ」的なものにBeckが再び取り組んだ作品であろう。Beck個人と言うよりは後ろに「with
Dust Brothers」と加えるべきではないかと言うくらいヒップホップ、エレクトリックが上手く取り入れられ、それがBeckのメロディーとがっちり与し、2005年式のロックとしてしっかり鳴り響いている。また、1曲1曲が意外とコンパクトに出来ているが、サウンドの絡みが凄く濃厚なのでいいバランスになっていると思う。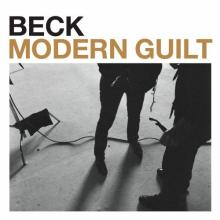 新作を出すごとに過剰なまでの期待をされるアーティストの一人がBeckだろう。それでも、デビューしてからすでに10年以上。相変わらずBeckの新作は、ロックの最前線であり、試金石である。
新作を出すごとに過剰なまでの期待をされるアーティストの一人がBeckだろう。それでも、デビューしてからすでに10年以上。相変わらずBeckの新作は、ロックの最前線であり、試金石である。 トレバー・ホーン・プロデュースのベルセバ待望の新作。前作「私の中の悪魔」あたりから、よりメロディーのポップさを素直に出していくようになってきたが、今作はさらにポップさに磨きがかかっている。あまりの聴きやすさに思わず面食らってしまった。ポップ・アルバムとしては完璧に近い仕上がりであるが、これがベルセバ本来の魅力かと言えば少し違うような気もする。ベルセバを聴くときは甘い毒を喉元に流し込まれているような感覚があったが、今回の作品はなにか爽やかにサイダーを飲んでいるような感じなのだ。訳詞を読むと、以前のような毒々しさも残っているが、ベルセバファンにとっては少し物足りないのではないかと思う。
トレバー・ホーン・プロデュースのベルセバ待望の新作。前作「私の中の悪魔」あたりから、よりメロディーのポップさを素直に出していくようになってきたが、今作はさらにポップさに磨きがかかっている。あまりの聴きやすさに思わず面食らってしまった。ポップ・アルバムとしては完璧に近い仕上がりであるが、これがベルセバ本来の魅力かと言えば少し違うような気もする。ベルセバを聴くときは甘い毒を喉元に流し込まれているような感覚があったが、今回の作品はなにか爽やかにサイダーを飲んでいるような感じなのだ。訳詞を読むと、以前のような毒々しさも残っているが、ベルセバファンにとっては少し物足りないのではないかと思う。


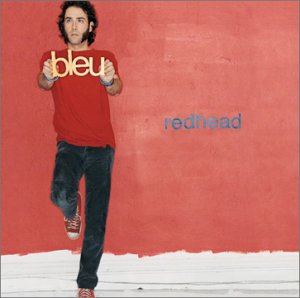 ボストン出身のシンガーソングライターであるブルウのデビューアルバム。ポップを基本線としながらも曲調は実に幅広く、ソングライティングの才能を感じさせるのには充分だ。元気の良いバブルガム・ポップから、大陸的なメロディーのナンバーまであるが、不思議な統一感がある。今回は、元ジェリーフィッシュのアンディー・スターマーを担ぎ出してのレコーディングだったそうだ。その目の付け所から、大体音も想像できると思う。前半にどキャッチーなナンバーを配しているため、後半ちょっとダレ気味になるところもあるが、この元気の良さと、ソングライティングの才能は作品の中で大いに光っているところである。
ボストン出身のシンガーソングライターであるブルウのデビューアルバム。ポップを基本線としながらも曲調は実に幅広く、ソングライティングの才能を感じさせるのには充分だ。元気の良いバブルガム・ポップから、大陸的なメロディーのナンバーまであるが、不思議な統一感がある。今回は、元ジェリーフィッシュのアンディー・スターマーを担ぎ出してのレコーディングだったそうだ。その目の付け所から、大体音も想像できると思う。前半にどキャッチーなナンバーを配しているため、後半ちょっとダレ気味になるところもあるが、この元気の良さと、ソングライティングの才能は作品の中で大いに光っているところである。 まず1曲目「Like Eating
Grass」のイントロを聴いて欲しい。ここでゾクゾクわき上がるカタルシスを感じる人は、終始このアルバムにやられることになる。逆に何も感じない人はそこで聞くのを止めた方がいいかもしれない。
まず1曲目「Like Eating
Grass」のイントロを聴いて欲しい。ここでゾクゾクわき上がるカタルシスを感じる人は、終始このアルバムにやられることになる。逆に何も感じない人はそこで聞くのを止めた方がいいかもしれない。
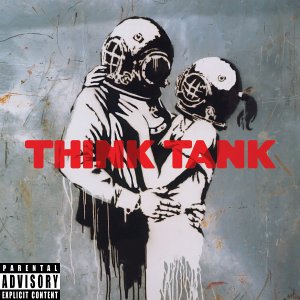 「ごめんよ・・・デーモン」とまず言いたい。新作に対しては当初、あまり期待していなかった。というのもデーモンがきっとゴリラズや最近のマリへのアプローチをかなりブラーに持ち込んできていて、ブラーの持つバンドのグルーヴがきっと損なわれていると思っていたし、グレアム・コクソンの脱退がそれに拍車をかけていると勝手に想像していたからだ。ゴリラズもあんまり好きではなかったし、ワールドミュージックというものが体質に合わない僕としては、きっと「デーモンが一人ごちた作品を作るのだろう」と大いに不安を感じていたのだ。
「ごめんよ・・・デーモン」とまず言いたい。新作に対しては当初、あまり期待していなかった。というのもデーモンがきっとゴリラズや最近のマリへのアプローチをかなりブラーに持ち込んできていて、ブラーの持つバンドのグルーヴがきっと損なわれていると思っていたし、グレアム・コクソンの脱退がそれに拍車をかけていると勝手に想像していたからだ。ゴリラズもあんまり好きではなかったし、ワールドミュージックというものが体質に合わない僕としては、きっと「デーモンが一人ごちた作品を作るのだろう」と大いに不安を感じていたのだ。 注文はいくらでもある。
注文はいくらでもある。 全米を皮切りに行われた、ペットサウンズ再現ツアーであるが、これはロンドンで行われた公演を収録。話によると東京公演の方が出来が良かったと言うことだが、以前にも書いたとおり当時からビーチボーイズを正当に評価していた国へのリスペクトということだろう。このライブを見に来たメンツもすごい。まあ、エリック・クラプトンやロジャー・ダルトリーはわかる。エルビス・コステロ、レイ・デイヴイスも。しかしこれだけにはとどまらない。リチャード・アシュクロフト(そういえば最近ブライアンとコラボレートしたという噂が)、マニックスのジェームズ、ケミブラ、TFC、スーファリのグラッフ、リチャード・ジェームス、ポール・ウェラー、ショーン・オヘイガン、意外なところではケビン・シールズにボビー・ギレスピーのプライマル組、スーパーグラスなど。やっぱりね、わかっているんだな。
全米を皮切りに行われた、ペットサウンズ再現ツアーであるが、これはロンドンで行われた公演を収録。話によると東京公演の方が出来が良かったと言うことだが、以前にも書いたとおり当時からビーチボーイズを正当に評価していた国へのリスペクトということだろう。このライブを見に来たメンツもすごい。まあ、エリック・クラプトンやロジャー・ダルトリーはわかる。エルビス・コステロ、レイ・デイヴイスも。しかしこれだけにはとどまらない。リチャード・アシュクロフト(そういえば最近ブライアンとコラボレートしたという噂が)、マニックスのジェームズ、ケミブラ、TFC、スーファリのグラッフ、リチャード・ジェームス、ポール・ウェラー、ショーン・オヘイガン、意外なところではケビン・シールズにボビー・ギレスピーのプライマル組、スーパーグラスなど。やっぱりね、わかっているんだな。 ついに出てしまったとでも言うべきか、あり得ない話が実現してしまったとでも言おうか。ここ最近のBrian周辺は実に充実したメンバーを抱えていて、Petsoundsの再現ライヴなど、これまでアンタッチャブルとされてきた企画をやれるだけの環境が整っている。それでも、この最大のアンタッチャブルには手をつけないだろうと思っていたが、ついに。
ついに出てしまったとでも言うべきか、あり得ない話が実現してしまったとでも言おうか。ここ最近のBrian周辺は実に充実したメンバーを抱えていて、Petsoundsの再現ライヴなど、これまでアンタッチャブルとされてきた企画をやれるだけの環境が整っている。それでも、この最大のアンタッチャブルには手をつけないだろうと思っていたが、ついに。
 2枚同時に発売されたアコースティックな方が本作品。1曲1曲紡がれていく物語は、カントリー的な曲調とは裏腹にとても重い。ただこの手のものがしばし陥りがちな重すぎて一枚聴き通すのが困難という欠点はこのアルバムにはない。それはまず、メロディーが素晴らしいことが大きな理由だと思う。シンプルながら本当に良い曲を書く。アメリカの伝統的なスタイルを踏襲しているため、大きく外すことはないという安定感もあるが、コナー・オバーストのメロディーは聴き手の心を鷲づかみにするのではなく、優しく包み込むような、そんな良さがある。これは「癒し」と言うことではなくて、コナーのリスナーとの独特な距離感がそう感じさせているのだと思う。強引に迫っていくのではなく、お互いの距離をお互いの「想像力」で埋めていこうという、そういったアプローチではないだろうか。
2枚同時に発売されたアコースティックな方が本作品。1曲1曲紡がれていく物語は、カントリー的な曲調とは裏腹にとても重い。ただこの手のものがしばし陥りがちな重すぎて一枚聴き通すのが困難という欠点はこのアルバムにはない。それはまず、メロディーが素晴らしいことが大きな理由だと思う。シンプルながら本当に良い曲を書く。アメリカの伝統的なスタイルを踏襲しているため、大きく外すことはないという安定感もあるが、コナー・オバーストのメロディーは聴き手の心を鷲づかみにするのではなく、優しく包み込むような、そんな良さがある。これは「癒し」と言うことではなくて、コナーのリスナーとの独特な距離感がそう感じさせているのだと思う。強引に迫っていくのではなく、お互いの距離をお互いの「想像力」で埋めていこうという、そういったアプローチではないだろうか。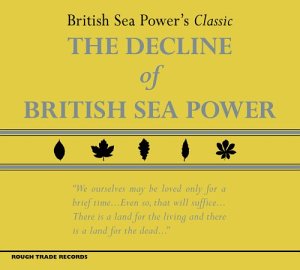 バンド名はあまりいかしていないが、ブライトン出身のバンド。雑誌等を見ても「ジョイ・ディヴィジョン」「スミス」あたりがポンポン出てくるので、かなり高い期待を持って聞いたが最初は、どパンクにしか聞こえなくて戸惑った(いや、悪くはないんだけど)。しかし、4曲目「Something
Wicked」あたりから、パワーポップの要素が、7曲目「The
Lonely」から、UK特有のエモーショナルなギターロックが、この辺はすごくツボをついてきてかなり好きな感じである。終盤にかけては、いよいよパンクの要素はなくなり、メランコリックなメロディーの曲が並ぶ。まるで、トイ・ドールズが最後はフランク&ウォルターズになってしまうような感じだ。
バンド名はあまりいかしていないが、ブライトン出身のバンド。雑誌等を見ても「ジョイ・ディヴィジョン」「スミス」あたりがポンポン出てくるので、かなり高い期待を持って聞いたが最初は、どパンクにしか聞こえなくて戸惑った(いや、悪くはないんだけど)。しかし、4曲目「Something
Wicked」あたりから、パワーポップの要素が、7曲目「The
Lonely」から、UK特有のエモーショナルなギターロックが、この辺はすごくツボをついてきてかなり好きな感じである。終盤にかけては、いよいよパンクの要素はなくなり、メランコリックなメロディーの曲が並ぶ。まるで、トイ・ドールズが最後はフランク&ウォルターズになってしまうような感じだ。 これはいいですね。まず何がいいって「Open Season」というアルバムタイトル。春にぴったりじゃないですか。そして不思議な生命力を感じるタイトルでもあります。でも、このことが実は凄く重要なキーワードになっているとも僕は思います。というのは、今回のアルバム全体にすごく有機的な流れを感じるのです。ステージ上に緑を飾る彼ら。彼らは鳥や草・木・花の一つ一つのエネルギーのような物を自然に感じ取り、表現のパワーに昇華させているのだと思います。そして、今回のアルバムはその点が前作よりも色濃く表れているように感じられます。だから、サイケデリックとオーガニックの不思議な同居とでも言いましょうか。詩はもうどうしようもなく八方ふさがりだったり、やるせなかったり、壊れたりしているんですが、サウンドと融合すると不思議な味わいを見せます。BSPサウンドとしか言いようのない存在感のある音です。
これはいいですね。まず何がいいって「Open Season」というアルバムタイトル。春にぴったりじゃないですか。そして不思議な生命力を感じるタイトルでもあります。でも、このことが実は凄く重要なキーワードになっているとも僕は思います。というのは、今回のアルバム全体にすごく有機的な流れを感じるのです。ステージ上に緑を飾る彼ら。彼らは鳥や草・木・花の一つ一つのエネルギーのような物を自然に感じ取り、表現のパワーに昇華させているのだと思います。そして、今回のアルバムはその点が前作よりも色濃く表れているように感じられます。だから、サイケデリックとオーガニックの不思議な同居とでも言いましょうか。詩はもうどうしようもなく八方ふさがりだったり、やるせなかったり、壊れたりしているんですが、サウンドと融合すると不思議な味わいを見せます。BSPサウンドとしか言いようのない存在感のある音です。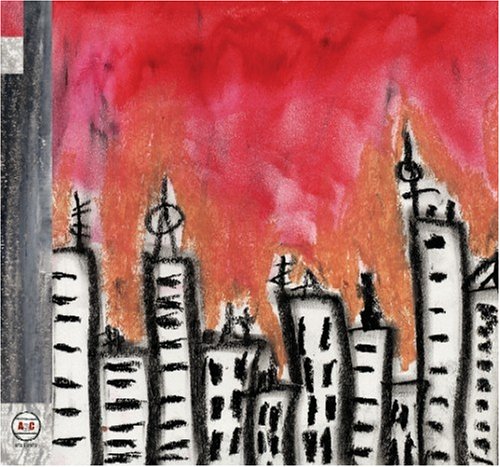
 バンプ待望の新曲。擦り切れんばかりに聴いた(とはいってもCDだから擦り切れないんだけど)「FLAME
VEIN」「THE LIVING
DEAD」の両アルバム、「ダイヤモンド」、「天体観測」といった傑作シングルたち。生きていくことを問うていく言葉、そしてその言葉を伝えるためのリズムとサウンド、この両面が奇跡的なバランスを保ち続けている数少ないバンドであり、数少ない中でも希有な存在であるバンプ。藤原基央は雑誌のインタービューで「知識、愛情、勇気、夢、そういうもの全部余計ですよ。結局のところ、どう切っても最高であり最強な歌を鳴らせるんだって事実と衝動だけが今は大切です」というようなことを言っていた。「ハルジオン」はまさにそのことを体現した歌だ。世の中では「夢を持て」「希望に向かって走れ」などといった薄っぺらい言葉が今でも正義面をしてまかり通っているのだが、僕らはその言葉にずっと違和感を抱えながら生きていたはずだ(と思う)。上手く言葉にできないのだけれど、結局のところただ自分の信じる絶対的なものに向かって進んでいくしかないのだ。当然その道はスマートなものにはならないだろうし、転んだり迷ったり、血を流すこともある。それでも突き進まずに入られない、そんな衝動こそを大切にしていくべきなのではないかと思う。僕がバンプの作品から強く感じるのは、そういうことである。過去でも未来でもなく「イマ」を生きるために「枯れても 枯れない花」を咲かせる、混乱も矛盾もすべて抱えたまま走っていく。「ハルジオン」はそんな彼らの軌跡を描いた曲であると思う。迷わず聴け。
バンプ待望の新曲。擦り切れんばかりに聴いた(とはいってもCDだから擦り切れないんだけど)「FLAME
VEIN」「THE LIVING
DEAD」の両アルバム、「ダイヤモンド」、「天体観測」といった傑作シングルたち。生きていくことを問うていく言葉、そしてその言葉を伝えるためのリズムとサウンド、この両面が奇跡的なバランスを保ち続けている数少ないバンドであり、数少ない中でも希有な存在であるバンプ。藤原基央は雑誌のインタービューで「知識、愛情、勇気、夢、そういうもの全部余計ですよ。結局のところ、どう切っても最高であり最強な歌を鳴らせるんだって事実と衝動だけが今は大切です」というようなことを言っていた。「ハルジオン」はまさにそのことを体現した歌だ。世の中では「夢を持て」「希望に向かって走れ」などといった薄っぺらい言葉が今でも正義面をしてまかり通っているのだが、僕らはその言葉にずっと違和感を抱えながら生きていたはずだ(と思う)。上手く言葉にできないのだけれど、結局のところただ自分の信じる絶対的なものに向かって進んでいくしかないのだ。当然その道はスマートなものにはならないだろうし、転んだり迷ったり、血を流すこともある。それでも突き進まずに入られない、そんな衝動こそを大切にしていくべきなのではないかと思う。僕がバンプの作品から強く感じるのは、そういうことである。過去でも未来でもなく「イマ」を生きるために「枯れても 枯れない花」を咲かせる、混乱も矛盾もすべて抱えたまま走っていく。「ハルジオン」はそんな彼らの軌跡を描いた曲であると思う。迷わず聴け。 ロッキン・オン・ジャパン3月号の表紙は彼ら。四人の集合写真であるが、ここから匂い立つものはいったい何であろうか。メンバー全員21,2とうところだと記憶しているが、単なるバンドのメンバーという気がしない。これはもう「戦友」と言っていいのではないだろうか。それくらい強い関係で結ばれているのだと言うことが、この写真からは感じ取れる。
ロッキン・オン・ジャパン3月号の表紙は彼ら。四人の集合写真であるが、ここから匂い立つものはいったい何であろうか。メンバー全員21,2とうところだと記憶しているが、単なるバンドのメンバーという気がしない。これはもう「戦友」と言っていいのではないだろうか。それくらい強い関係で結ばれているのだと言うことが、この写真からは感じ取れる。 久しぶりにドロップされたシングルは、至ってストレートなラブソング。藤原のロマンチシズムがいかんなく発揮された作品である。手触りとしては2ndの「リリィ」に近い感じではないだろうか。少し恥ずかしくなるような内容ではあるが、こういう曲をさらりとやれてしまうのが彼らの強みであろう。
久しぶりにドロップされたシングルは、至ってストレートなラブソング。藤原のロマンチシズムがいかんなく発揮された作品である。手触りとしては2ndの「リリィ」に近い感じではないだろうか。少し恥ずかしくなるような内容ではあるが、こういう曲をさらりとやれてしまうのが彼らの強みであろう。 僕は「ワンピース」というマンガを読んだことも、アニメを見たこともない。見ようと思ったこともないし、まして見る必要があると思ったこともない。「Sailing
Day」が「ワンピース」の主題歌になったという話もあまり重要に考えてはいなかったが、この詩の世界を読み解くためには重要なタームであるといえるだろう。もろタイアップを意識したと言うことだから、それはそれでいいのだが、ちょっとした疎外感も感じてしまった。
僕は「ワンピース」というマンガを読んだことも、アニメを見たこともない。見ようと思ったこともないし、まして見る必要があると思ったこともない。「Sailing
Day」が「ワンピース」の主題歌になったという話もあまり重要に考えてはいなかったが、この詩の世界を読み解くためには重要なタームであるといえるだろう。もろタイアップを意識したと言うことだから、それはそれでいいのだが、ちょっとした疎外感も感じてしまった。 Bump
Of Chicken、明らかに一つハードルを越えた作品。「Flame Vein」「The Living
Dead」の初期2作があまりにも痛烈で瑞々しくて、少年の残酷性を持ったアルバムであったために、前作「Jupiter」は僕の中でどこか焦点がぼけた作品としてうつっていた。「ダイヤモンド」「ハルジオン」など名曲があるものの、アルバムの各曲が織りなすストーリーが平坦であったり、無理があったためにメロディーも昇華しきれないところがあった。
Bump
Of Chicken、明らかに一つハードルを越えた作品。「Flame Vein」「The Living
Dead」の初期2作があまりにも痛烈で瑞々しくて、少年の残酷性を持ったアルバムであったために、前作「Jupiter」は僕の中でどこか焦点がぼけた作品としてうつっていた。「ダイヤモンド」「ハルジオン」など名曲があるものの、アルバムの各曲が織りなすストーリーが平坦であったり、無理があったためにメロディーも昇華しきれないところがあった。