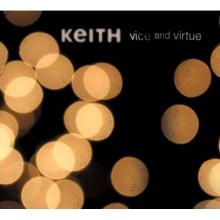 マンチェスター出身のバンド、Keithのセカンド。1st「Red Thread」はSmiths直系のギター・バンド的な要素や、クラウト・ロックなど自分たちの感性にふれるものを上手く融合して、自分たちの世界観を作ることに成功した、いいアルバムだった。不思議な暖かみや憂いを含んだメロディーラインも個人的にはツボでとても期待していたんだけど、シーンの主流になることはなく、何となく地味に消えていったような印象がある。
マンチェスター出身のバンド、Keithのセカンド。1st「Red Thread」はSmiths直系のギター・バンド的な要素や、クラウト・ロックなど自分たちの感性にふれるものを上手く融合して、自分たちの世界観を作ることに成功した、いいアルバムだった。不思議な暖かみや憂いを含んだメロディーラインも個人的にはツボでとても期待していたんだけど、シーンの主流になることはなく、何となく地味に消えていったような印象がある。
しかしながら、彼らは素晴らしいアルバムを抱えて、またシーンに戻ってきた。アルバム中の数曲を、フランツ・フェルディナンドの最新作をプロデュースしたダン・キャリーが手がけている
1曲目「can't See the
faces」から、重めのリフやオルガンが炸裂している。そしてこの曲だけでなく、全体的に1stと比べるとかなりダークな方へと向かった感がある。ギターリフも前作の浮遊感やサイケデリックな雰囲気を生むような役割ではなく、刹那的というか非常に攻撃性を感じさせる力強いものに変貌している。
ソングライティングの部分は相変わらず申し分ない。前作と比べるとややオリエンテッドな部分が増え、そこが今作のトーンといいマッチングを見せている。
サウンドが全体的に骨太になったが、変な重苦しさは感じない。タイトル通り悪徳と美徳の合間を揺れ動くような人間の「陰」の部分を表現するためには、必要なビルドアップであったように思う。
今作にしてもやはりシーンの主流からはかなり遠いところにある音だ。でも、何の迷いもなくこういう音を鳴らせるバンドもシーンには必要なのだ。このダークなサウンドはとてつもない美を湛えている。この素晴らしさに一人でも多くの人が触れてくれたら、とても嬉しい。
おすすめ度★★★★(27/12/08)
up
in the clouds
lullaby
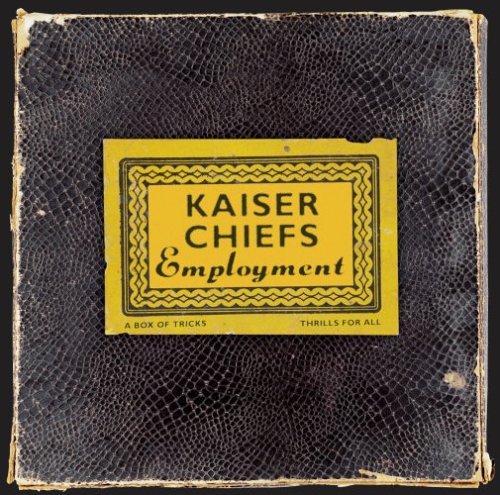 フランツがこれまでのUKロックが培ってきた「歌もの」的要素を、ユーモアとウィットを巧みに取り入れながら形にしていき、結果的に耳にこびりついて離れない「歌」へと昇華させたのに対して、このKaiser
Chiefsはパンキッシュな要素に様々な部分から味付けを施し、奇天烈なポップに仕上げている。そこがやはりこのバンドの最大の個性だろう。たしかに歌メロはよい。しかし、むしろ目に付くのは曲ごとに随所に観られる「遊び心」である。チープなシンセ、チープなコーラスそのどれもが必殺のフレーズとして鳴っている。そしてこの「遊び心」こそ、ブリットポップが残した財産ではないかと思うのだ。
フランツがこれまでのUKロックが培ってきた「歌もの」的要素を、ユーモアとウィットを巧みに取り入れながら形にしていき、結果的に耳にこびりついて離れない「歌」へと昇華させたのに対して、このKaiser
Chiefsはパンキッシュな要素に様々な部分から味付けを施し、奇天烈なポップに仕上げている。そこがやはりこのバンドの最大の個性だろう。たしかに歌メロはよい。しかし、むしろ目に付くのは曲ごとに随所に観られる「遊び心」である。チープなシンセ、チープなコーラスそのどれもが必殺のフレーズとして鳴っている。そしてこの「遊び心」こそ、ブリットポップが残した財産ではないかと思うのだ。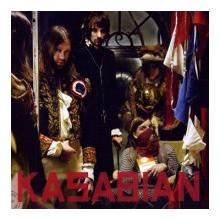
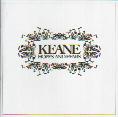 端的に言うと、ColdplayやTravisが好きな人なんかは素通りできない音であると思う。ギターレスでピアノが中心となった3ピースバンド。強烈な個性があるというわけではないが、メロディーの良さ、ピアノ中心ながらダイナミックさを内包しているサウンドは最近の新人の中でも、クオリティーが高い。特にメロディーには、メランコリックながら不思議な力強さがある。こういう凛とした強さを持った曲達がこのアルバムにはたくさん並んでいる。Starsailorの2ndなんかを想像していただけるといいのではないかと思う。この手のバンドの中で、ここまで新鮮に感じるのも本当に少ない。つまり聴き手の陳腐な先入観を吹き飛ばしてくれる、そんな力を持った音楽だ。
端的に言うと、ColdplayやTravisが好きな人なんかは素通りできない音であると思う。ギターレスでピアノが中心となった3ピースバンド。強烈な個性があるというわけではないが、メロディーの良さ、ピアノ中心ながらダイナミックさを内包しているサウンドは最近の新人の中でも、クオリティーが高い。特にメロディーには、メランコリックながら不思議な力強さがある。こういう凛とした強さを持った曲達がこのアルバムにはたくさん並んでいる。Starsailorの2ndなんかを想像していただけるといいのではないかと思う。この手のバンドの中で、ここまで新鮮に感じるのも本当に少ない。つまり聴き手の陳腐な先入観を吹き飛ばしてくれる、そんな力を持った音楽だ。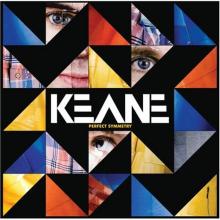
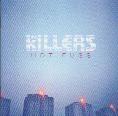 1曲目「Jenny Was A Friend Of Mine」はイントロのシンセがDURAN DURANの「Planet
Earth」のように聞こえ、「ここまでやったか」とほくそ笑んでしまった。明らかに80年代のニューロマの影響が色濃いバンドです。僕も小学生の時はこの手の音をむさぼるように聞いていたたちなので、曲が進むたびに「これは○○だ」と元ネタ探しだけでもかなり楽しいですが、単なる模倣だけではなく、今のシーンを反映したややパンキッシュなところもかいま見られます。しかし、基調はあくまでシンセとギターのキャッチーなフレーズが同格で絡み合うサウンド。そしてヴォーカルもまさに80年代の演歌ポップ的歌い回し。時々こういう音が聞きたくなる僕としてはなかなか楽しく聞けました。第2次ブリティッシュ・インヴェイジョンに洗礼を受けた人には聞いて欲しい一枚ではある。ただ、バンドとしての個性をどこに見いだすか。Duran
Duranのアルバムではなく、Killersが聞きたいと思わせるだけの魅力をこのアルバムが持っているか。そこは苦しいと言わざるを得ない。もっともっと下世話なところを出すか、キラーチューンと呼べるものを生み出すか、どちらも道は険しいが、これがこのバンドの生きる道だと思う。
1曲目「Jenny Was A Friend Of Mine」はイントロのシンセがDURAN DURANの「Planet
Earth」のように聞こえ、「ここまでやったか」とほくそ笑んでしまった。明らかに80年代のニューロマの影響が色濃いバンドです。僕も小学生の時はこの手の音をむさぼるように聞いていたたちなので、曲が進むたびに「これは○○だ」と元ネタ探しだけでもかなり楽しいですが、単なる模倣だけではなく、今のシーンを反映したややパンキッシュなところもかいま見られます。しかし、基調はあくまでシンセとギターのキャッチーなフレーズが同格で絡み合うサウンド。そしてヴォーカルもまさに80年代の演歌ポップ的歌い回し。時々こういう音が聞きたくなる僕としてはなかなか楽しく聞けました。第2次ブリティッシュ・インヴェイジョンに洗礼を受けた人には聞いて欲しい一枚ではある。ただ、バンドとしての個性をどこに見いだすか。Duran
Duranのアルバムではなく、Killersが聞きたいと思わせるだけの魅力をこのアルバムが持っているか。そこは苦しいと言わざるを得ない。もっともっと下世話なところを出すか、キラーチューンと呼べるものを生み出すか、どちらも道は険しいが、これがこのバンドの生きる道だと思う。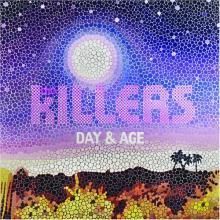
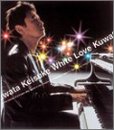 「日本のミュージシャンでメロディメーカーといえば・・・」ということを考えるときにまず始めに浮かぶのは、スピッツの草野マサムネである。次に宮本弘次かな。いつも中毒性をもついいメロディを書くなーと感心している2人である。
「日本のミュージシャンでメロディメーカーといえば・・・」ということを考えるときにまず始めに浮かぶのは、スピッツの草野マサムネである。次に宮本弘次かな。いつも中毒性をもついいメロディを書くなーと感心している2人である。 かなり売れているらしい。たぶんなんだかんだで耳にしているでしょう。みんなの期待を大きく裏切った今回のシングル。ジャパンのシングル評でさえも疑問符を付けていたが、本当のサザン・桑田ファンであるならきっと読めた展開であると思う。「女神たちの情歌」「イエローマン」のような、いわゆる桑田の趣味性の強いものをこうやって時々シングルにする、桑田のお得意のパターンだ。
かなり売れているらしい。たぶんなんだかんだで耳にしているでしょう。みんなの期待を大きく裏切った今回のシングル。ジャパンのシングル評でさえも疑問符を付けていたが、本当のサザン・桑田ファンであるならきっと読めた展開であると思う。「女神たちの情歌」「イエローマン」のような、いわゆる桑田の趣味性の強いものをこうやって時々シングルにする、桑田のお得意のパターンだ。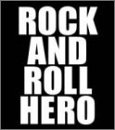 桑田佳祐を語る上で、いつまでも忘れられないエピソードがある。それはある雑誌でチャボが「桑田君って政治がどうとか社会がこうだとか絶対に歌わないでしょ。だからすごい興味がある。」と語ったことである。幼稚園の頃から「勝手にシンドバッド」に目覚め、スミスやR.E.M、果てはXTCを貪りつつも、ずっとサザンに虜になってきた人間にとってはまさに最大級の賛辞であった。確かに桑田佳祐という人は長い間音楽界をサヴァイヴする中で、社会的なメッセージソングを歌おうとはしなかったし(いや、厳密に言えば残留孤児のことを歌った「かしの木の下で」などがあるが)、一時期異常に流行ったチャリティー的な活動(有名なのはバンド・エイド)についても、批判的な発言などもしながら手を染めようとはしなかった。その理由はこれらの行為がいわゆる一元論的な「正義」や、押しつけまたは自己満足に過ぎない「善意」であるという本質を見抜いていたからである。そして、これは山下達郎の言葉であるが「歌は世につれるが、世は歌につれない」というポップソングの立ち位置を第一線で活躍する立場として痛感していたというのも大きい。自分の求める音楽に対して恐ろしくストイックであるが故に、枷となるようなメッセージ性は排除しようとしていたのだろう。しかし、国民的バンドとしてその期待を一新に背負い、「みんなのうた」を量産し続ける中で、桑田佳祐という個に対しては意外なほど目を向けられてこなかったような気がする。サザンのナンバーから国民が感じ取る「陽性」なイメージとは逆に、桑田佳祐という人はいかがわしさ、猥雑さといった強烈な「陰」のパワーを持った人である。桑田佳祐自身は己の作品においてそのパワーをいかんなく発揮してきたが、それに気づいていた人はどれくらいいたであろうか。世を席巻してきたポップソングの裏にはもうどうしようもない桑田佳祐のパーソナルが毒が渦巻いているのである。
桑田佳祐を語る上で、いつまでも忘れられないエピソードがある。それはある雑誌でチャボが「桑田君って政治がどうとか社会がこうだとか絶対に歌わないでしょ。だからすごい興味がある。」と語ったことである。幼稚園の頃から「勝手にシンドバッド」に目覚め、スミスやR.E.M、果てはXTCを貪りつつも、ずっとサザンに虜になってきた人間にとってはまさに最大級の賛辞であった。確かに桑田佳祐という人は長い間音楽界をサヴァイヴする中で、社会的なメッセージソングを歌おうとはしなかったし(いや、厳密に言えば残留孤児のことを歌った「かしの木の下で」などがあるが)、一時期異常に流行ったチャリティー的な活動(有名なのはバンド・エイド)についても、批判的な発言などもしながら手を染めようとはしなかった。その理由はこれらの行為がいわゆる一元論的な「正義」や、押しつけまたは自己満足に過ぎない「善意」であるという本質を見抜いていたからである。そして、これは山下達郎の言葉であるが「歌は世につれるが、世は歌につれない」というポップソングの立ち位置を第一線で活躍する立場として痛感していたというのも大きい。自分の求める音楽に対して恐ろしくストイックであるが故に、枷となるようなメッセージ性は排除しようとしていたのだろう。しかし、国民的バンドとしてその期待を一新に背負い、「みんなのうた」を量産し続ける中で、桑田佳祐という個に対しては意外なほど目を向けられてこなかったような気がする。サザンのナンバーから国民が感じ取る「陽性」なイメージとは逆に、桑田佳祐という人はいかがわしさ、猥雑さといった強烈な「陰」のパワーを持った人である。桑田佳祐自身は己の作品においてそのパワーをいかんなく発揮してきたが、それに気づいていた人はどれくらいいたであろうか。世を席巻してきたポップソングの裏にはもうどうしようもない桑田佳祐のパーソナルが毒が渦巻いているのである。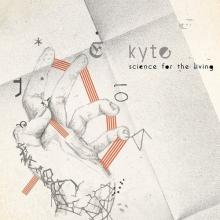 UKはレスター出身、Kyteの2nd。平均年齢が21歳とのことで、現在のシーンではそう珍しいことではないが、彼らの作り出す音が醸し出す「貫禄」を考えると、相当に若いように思える。つまりは、とても20そこそこの若者が作り出したとは思えないほどの壮大なサウンドスケープがこのアルバムで展開されているのだ。
UKはレスター出身、Kyteの2nd。平均年齢が21歳とのことで、現在のシーンではそう珍しいことではないが、彼らの作り出す音が醸し出す「貫禄」を考えると、相当に若いように思える。つまりは、とても20そこそこの若者が作り出したとは思えないほどの壮大なサウンドスケープがこのアルバムで展開されているのだ。