 Mando Diaoの5rd。意外とコンスタントに出し続けているせいか、もう5枚もリリースしているんですね。そうはいっても、破格のロックンロールで北欧から我々をロックの臨界点へと連れて行った1stに比べるとその後は決して満足のいくものではなかった。いきなりすごい物をドロップしてしまった後に陥りやすい袋小路に彼らは見事にはまってしまった。ここまでの変遷には彼ら自身はそれなりに自信を持っていると思う。ただ、それが聴き手の心情とがっちりリンクしていたかというと、少々ズレが生じていたと思うのだ。
Mando Diaoの5rd。意外とコンスタントに出し続けているせいか、もう5枚もリリースしているんですね。そうはいっても、破格のロックンロールで北欧から我々をロックの臨界点へと連れて行った1stに比べるとその後は決して満足のいくものではなかった。いきなりすごい物をドロップしてしまった後に陥りやすい袋小路に彼らは見事にはまってしまった。ここまでの変遷には彼ら自身はそれなりに自信を持っていると思う。ただ、それが聴き手の心情とがっちりリンクしていたかというと、少々ズレが生じていたと思うのだ。
前作がもうかなり遠いところへ行ってしまったので、今作は最初買おうかどうかさえ迷っていたところであった。しかし、これは久しぶりにマンドゥが「マンドゥらしさ」を取り戻した作品だと思う。
それでは「マンドゥらしさ」とは何ぞや、ということであるが、僕は「グスタフが吠え、ビョルンが泣いている」この一点に尽きると思う。ソングライターであり、ヴォーカリストであるこの2人の魅力はそこにあると思う。1stのSheepdogではグスタフが暴れ犬のような粗暴なヴォーカリゼーションを見せれば、Mr.Moonではビョルンが男の泣きを哀愁たっぷりに歌い上げていた。こういったある種の二面性が、マンドゥの魅力であった。そして、今作もそこに忠実に作られていると思う。
1曲目Blue Lining, White Trenchcoatの地を這うようなベースラインと、
グスタフの王道のロックヴォーカル。これを聴いてまず安心する。厳ついメロディーに独特の叙情性が重なったいかにもマンドゥらしいナンバーだ。
そして期待しながらも度肝を抜かれたのが、3曲目Gloriaのコテコテの演歌っぷり。60〜70年代の歌謡曲のようなベタベタなメロディー。西城秀樹なんかが歌っても全く違和感のない反則スレスレのナンバーだ。しかしながら、僕はこういうナンバーこそがマンドゥの真骨頂であるように思う。ここでのビョルンの泣きっぷりはもうお見事である。
それでも、これは原点回帰作ではない。あくまでもこれまでの歩みを自分たちのロックンロールへと昇華させることに成功した素晴らしいアルバムだ。
例えば、リードトラックであるDance With
Somebodyはフランツかと思うくらい妖艶な魅力を湛えたタイトでダンサブルなナンバー。これがとてもバンドにマッチした感じに仕上がっている。Mean
Streetはシンプルなロックンロールだけど、メロディーは割とモータウンっぽいポップな感じで楽しい1曲。ラストナンバー、The
Shiningはマンドゥなりのブラス・ロック・シンフォニー。少々くどい感じもあるが、ラストを締めると言う点においてはこれ以外にはないというくらいはまっている。
もっともっと暴れていいんじゃないかとも思うが、久しぶりに抜けの良いロックンロールを聴かせてくれたことは実にうれしい。この勢いを持ち込んだパフォーマンスをサマソニでも是非。
おすすめ度★★★★(03/03/09)
Review M -
|
||||||
 これもまた中毒性が高いアーティストです。あちこちで評判になっていますが、ラップスティールギターの調べと、サンプリングやストリングスを多用したバックトラックに乗せて、美しいメロディーと流麗なヴォーカルを聴かせてくれる。ノルウェー出身らしい極北の冷え切った美しい夜空のサウンドトラックのようだ。特にストリングスの使い方が上手いなと思っていたら、クレジットになんとショーン・オヘイガンの名前が。なるほど納得。 これもまた中毒性が高いアーティストです。あちこちで評判になっていますが、ラップスティールギターの調べと、サンプリングやストリングスを多用したバックトラックに乗せて、美しいメロディーと流麗なヴォーカルを聴かせてくれる。ノルウェー出身らしい極北の冷え切った美しい夜空のサウンドトラックのようだ。特にストリングスの使い方が上手いなと思っていたら、クレジットになんとショーン・オヘイガンの名前が。なるほど納得。アルバム全編通して、ミドルテンポの曲が多いが、不思議と飽きずに何回でも聴けてしまう。それは、1曲1曲が強烈な世界を持っているからだと思う。時に壮大に、時にリリカルに、バラエティにも富んだ曲を書けるのも彼の強みとなるだろう。「ザ・デイ・ウィー・レフト・タウン」「スマイル・トゥ・ザ・ワールド」は超名曲。 おすすめ度★★★★(03/8/6) |
||||||
|
||||||
 真心の「別れの歌・3部作」と「明日はどっちだ」をまとめたミニアルバム。最近ずっとソウル・ファンク路線できた真心でしたが、「別れの歌3部作」では、フォーキーなサウンドに男の揺れる感情を載せるという、「今の時代にそれやっちゃうか〜」と思わずにいられない、ストレートな歌を聴かせてくれました。「夢ではなく 嘘でもない 俺はもう 死にたかった」「君がいないと 俺の心はもうじき死ぬだろう 助けて」(「遠い夏」より)いやー情けねーとも思ってしまうのですが、本当はすごく好きです。男気のあるラブソングが好きな人(俺!!)、必聴。特に「流れ星」と「遠い夏」、YO-KING作のこの2曲、アルバムの1,2曲目ですので、ぜひ聴いてください。吉田拓郎のカバーもありますが、これはもろフォーク。 真心の「別れの歌・3部作」と「明日はどっちだ」をまとめたミニアルバム。最近ずっとソウル・ファンク路線できた真心でしたが、「別れの歌3部作」では、フォーキーなサウンドに男の揺れる感情を載せるという、「今の時代にそれやっちゃうか〜」と思わずにいられない、ストレートな歌を聴かせてくれました。「夢ではなく 嘘でもない 俺はもう 死にたかった」「君がいないと 俺の心はもうじき死ぬだろう 助けて」(「遠い夏」より)いやー情けねーとも思ってしまうのですが、本当はすごく好きです。男気のあるラブソングが好きな人(俺!!)、必聴。特に「流れ星」と「遠い夏」、YO-KING作のこの2曲、アルバムの1,2曲目ですので、ぜひ聴いてください。吉田拓郎のカバーもありますが、これはもろフォーク。おすすめ度★★★★(01/9/29) 夢の日々〜SERIOUS & JOY  活動停止を発表した彼らの最後(?)のアルバム。この前のミニアルバム「真心」に収録されている曲が5曲入っている。アルバムごとにその作風を変える彼らであるが、今回は「別れの歌3部作」の流れを踏襲している。僕はYO-KINGの声と詞が好きで、桜井がボーカルをとるナンバーはそれほど熱心に聞かなかったクチである。これまでのアルバムに関しても、なにか桜井のナンバーがアルバムのトータル性やクオリティに影響を与えてきたように感じている。傑作「KING
OF
ROCK」はまさにYO-KINGの力がメーターが振り切れんばかりに大爆発したいい例である。しかし、桜井色が強く出てしまうと、真心のアルバムはもう一つの品質となってしまうようにずっと思っていた。つまりYO-KINGのはじけっぷりこそが、真心を左右していると思っていた。 活動停止を発表した彼らの最後(?)のアルバム。この前のミニアルバム「真心」に収録されている曲が5曲入っている。アルバムごとにその作風を変える彼らであるが、今回は「別れの歌3部作」の流れを踏襲している。僕はYO-KINGの声と詞が好きで、桜井がボーカルをとるナンバーはそれほど熱心に聞かなかったクチである。これまでのアルバムに関しても、なにか桜井のナンバーがアルバムのトータル性やクオリティに影響を与えてきたように感じている。傑作「KING
OF
ROCK」はまさにYO-KINGの力がメーターが振り切れんばかりに大爆発したいい例である。しかし、桜井色が強く出てしまうと、真心のアルバムはもう一つの品質となってしまうようにずっと思っていた。つまりYO-KINGのはじけっぷりこそが、真心を左右していると思っていた。今回のアルバムはYO-KING10曲、桜井6曲。桜井の曲が結構多い。しかし、これまでのような散漫な感じを受けなかった。桜井作品が大健闘している。初期ユーミンのような「まばたきの間に」、ストレートなラブソング「名前を呼びたい」など、桜井の「うた」がすごく生きているのである。もちろんYO-KINGも健在で、相変わらず詞のセンスがさえている。メロディーもこれまでの作品の中で一番良い。ラストアルバムが、真心の新しい可能性を感じさせるものとなっているのが何とも皮肉だ。 おすすめ度★★★★(01/12/7) |
||||||
| Give Me Fire |
|
|
|
|
|
||||||
 マニックスが好きな人って「ジェネレーション・テロリスト」の頃からのファンも結構いるのだろうか?よくわからないのだが、僕にとってマニックスといえば未だに「4REAL」というイメージがぬぐいきれない。「全世界でナンバーワンになって即解散!」そんなセンセーショナルな見出しとともに彼らは登場した。「モータウン・ジャンク」(これ、一番好きです)というアンセムとともに。No1になって解散する、このことにいったい何の意味があるのか、とも思ったが、「モータウン・ジャンク」を繰り返し聞いていると実は彼らには「これ(解散)以外に意味のあることはない」ということに気づく。初期衝動が燃え尽きようとする瞬間にやめる、あくまで彼らはロックの理想の道を歩もうとしたのだと思った。そして、発売前、渋谷陽一のラジオで何曲か聴いたのだが正直「なんだこりゃ?」であった。元気はいいが、ちょっと安い感じのハードロック風、そんな印象を持った。「モーターサイクル・エンプティネス」は別格であったが、それ以外は明らかに「売れ線ねらっているな」と思った。あの時期待していた人たちはほとんど外されたと思ったろう。そして実際このアルバムはそこそこ売れるが1位になることはなく、しかも本国盤はおろか、日本盤さえ「モータウン・ジャンク」は収録されていなかったのだ。「がっくし」の一言であった。結果的に彼らは解散宣言を撤回し、リッチーを失いながらも国民的バンドへとのし上がっていく。 マニックスが好きな人って「ジェネレーション・テロリスト」の頃からのファンも結構いるのだろうか?よくわからないのだが、僕にとってマニックスといえば未だに「4REAL」というイメージがぬぐいきれない。「全世界でナンバーワンになって即解散!」そんなセンセーショナルな見出しとともに彼らは登場した。「モータウン・ジャンク」(これ、一番好きです)というアンセムとともに。No1になって解散する、このことにいったい何の意味があるのか、とも思ったが、「モータウン・ジャンク」を繰り返し聞いていると実は彼らには「これ(解散)以外に意味のあることはない」ということに気づく。初期衝動が燃え尽きようとする瞬間にやめる、あくまで彼らはロックの理想の道を歩もうとしたのだと思った。そして、発売前、渋谷陽一のラジオで何曲か聴いたのだが正直「なんだこりゃ?」であった。元気はいいが、ちょっと安い感じのハードロック風、そんな印象を持った。「モーターサイクル・エンプティネス」は別格であったが、それ以外は明らかに「売れ線ねらっているな」と思った。あの時期待していた人たちはほとんど外されたと思ったろう。そして実際このアルバムはそこそこ売れるが1位になることはなく、しかも本国盤はおろか、日本盤さえ「モータウン・ジャンク」は収録されていなかったのだ。「がっくし」の一言であった。結果的に彼らは解散宣言を撤回し、リッチーを失いながらも国民的バンドへとのし上がっていく。こう書くと、自分がすごくマニックスが嫌いなように思われるかもしれないが、決してそうではない。このベストアルバムを聴けばわかるように、ジェームズのソングライティング能力は尋常ではない。キャッチー度ではノエル・ギャラガー以上と断言できる。初期の曲はほとんど聴いたことがないが、やはりメロディーの構成が素晴らしい。若干演歌チックさを感じてしまい、のめり込むほど聴くところまでは行かないのだが、これだけいい曲の多いベスト盤も珍しい。もし彼らの1stが1位になって宣言通り解散していたら、これらの作品には巡り会うことがなかったのだと考えるとなんだか感慨深い。本当いいバンドだわ。 おすすめ度★★★☆(02/11/14) |
||||||
| Jounal For Plague Lovers |
|
 Manic Street Preachersの9th。前作「Send Away The Tigers」はセールス的にも大きな成功を収め、彼らの復活的作品としても大きな評価を得た。 Manic Street Preachersの9th。前作「Send Away The Tigers」はセールス的にも大きな成功を収め、彼らの復活的作品としても大きな評価を得た。
マニックスというと、意外とイメージの定まらないバンドだという印象を持っている。僕にとってのマニックスとは未だに「Motown Junk」であり、「4REAL」なのだが、そういうリスナーは今やごくわずかだろう。マニックスがシーンの中で大きな存在となり、国民的バンドとなったのはリッチー失踪後の「Everything Must Go」以降であり、今のリスナーには「A Design For Life」のようなドラマチックなロックを歌うバンドみたいなイメージの方が強いだろう。 しかしながら、彼らの今回の挑戦は「リッチー・エドワーズが残した詞を使って「Holy Bible」の続編となるアルバム」を作ることだった。マニックスのアルバムの中で最もパンキッシュであり、人を寄せ付けないようなヒリヒリとしたテンションを持った「Holy Bible」。リッチーの突然の失踪により、図らずも「悲劇のバンド」として国民的人気を得てしまった彼らにとって、その続編を作るということはやはり相当の時間が必要だったのだろう。 プロデューサーはスティーヴ・アルビニ。当然ながらアナログ・レコーディング。そういった環境からすでに、バンドとして妥協せず徹底的にソリッドな音作りを目指しているのがわかる。 ただ、個人的には続編的アルバムと言うよりは、今の彼らの姿が反映されたロック・アルバムというほうがしっくりくる。これまでの経験値、そして抱えてきた痛み、そういったものがサウンドからにじみ出てくるし、リッチーの詞も今の彼らが歌うことを予見していたかのような青さと成熟さ両面兼ね備えたようなものなのだ。 そしてサウンドの方も前作よりはぐっとラウドでエッジの立ったものへとなってはいるが、「Holy
Bible」よりはメロウな仕上がりとなっている。ボトムは図太く筋肉質な感じでありながら、時折のぞく繊細さも当時の怒れる若者には出せないものである。アルビニ・プロデュース作品の中でもここまで柔らかな要素のあるアルバムはそうないだろう。 おすすめ度★★★★(31/05/09) |
|
|
||||||
 実はMars Voltaのアルバムを買ったのは初めて。前に試聴したことはあったんだけど、どうも買おうとは思わなかった。そもそも、1曲1曲が長いのがあまり得意じゃない。だから、プログレなんかもあんまり聴かない。だから、サウンド的には結構ツボだったりするんだけど、敢えて聴かなかったのがMars voltaであった。 でも、新作は彼らにしては1曲1曲が割とコンパクトな尺におさめられている。長くても9分だ。それでいて、必ずどの曲にも強烈にキャッチーなサビがある。まるで、昔のハード・ロックのようなところがある。そう、たとえて言うならば、ツェッペリンの往年の名作のような佇まいがあるのだ。 実はMars Voltaのアルバムを買ったのは初めて。前に試聴したことはあったんだけど、どうも買おうとは思わなかった。そもそも、1曲1曲が長いのがあまり得意じゃない。だから、プログレなんかもあんまり聴かない。だから、サウンド的には結構ツボだったりするんだけど、敢えて聴かなかったのがMars voltaであった。 でも、新作は彼らにしては1曲1曲が割とコンパクトな尺におさめられている。長くても9分だ。それでいて、必ずどの曲にも強烈にキャッチーなサビがある。まるで、昔のハード・ロックのようなところがある。そう、たとえて言うならば、ツェッペリンの往年の名作のような佇まいがあるのだ。ドラマー脱退も今回のサウンドを聴く限り、その影響は感じられない。カオティックで凶暴なグルーヴはかなり中毒性が高い。どのパートもフリーキーでありながら、実に必然的な絡み方をしてくるのも素晴らしい。個人的には時折のたうつサックスがたまらない感じです。 ツェッペリンは最近素晴らしいパフォーマンスを見せたようだけど、今の20代くらいの人たちにとっては、Mars Voltaの方がしっくり来るのではないだろうか。それは、60年代、70年代のバンドがいかにしてジャンルに縛られない音楽・グルーヴを生み出すか、血のにじむような格闘を続けていたのに対し、Mars Voltaはそういった観念無しに、やりたいものを迷い無く音にしている感じである。それは、まさに全体がボーダーレス化しつつある現代に近い音だと思うのだ。なんでもあって、なんでもいい。そういう自由さは、もっとロックにあっても良いんじゃないかと思うし、Mars Voltaはまさにそのメンタリティーを体現していると思う。 ちなみに、僕が買ったのはデラックス・エディションで巷で話題のSHM-CDで、DVD付きである。その中にボートラが3曲入っている。どれもカバーなのだが、個人的にはシュガーキューブス(ビョークが在籍していたバンド)の「Birthday」が良かった。高校生の時、この曲好きだったんだよな。 おすすめ度★★★★☆(08/3/8) |
||||||
|
||||||
 「サイケデリック」という言葉で語られるバンドはたくさんいるけど、Mercury Revの存在はそれらの中でも孤高のものであるように思う。例えば万華鏡。パーツや色が少なくても織りなす光景は十分に美しく、ちょっとした幻想感を与えてくれる。しかしながら、彼らは自分の万華鏡に止めどなくパーツや色を足していく。もう十分だろうと周りが思っていても止めようとしない。数え切れないほどの音を、信じられないくらいの大音量で奏でてきたのだ。結果万華鏡は誰も見たことがないような極彩色に仕上がる。覗いた人は初めて見る光景に驚き、その正体を知ろうと足を踏み入れていくうちに、自分が今どこにいるのかも分からなくなる。それこそが彼らの体現する「ドリーミー」であると思う。これが癖になる人は、どこまでも彼らのサウンドにひたりたくなる。僕もその一人なのだが。 「サイケデリック」という言葉で語られるバンドはたくさんいるけど、Mercury Revの存在はそれらの中でも孤高のものであるように思う。例えば万華鏡。パーツや色が少なくても織りなす光景は十分に美しく、ちょっとした幻想感を与えてくれる。しかしながら、彼らは自分の万華鏡に止めどなくパーツや色を足していく。もう十分だろうと周りが思っていても止めようとしない。数え切れないほどの音を、信じられないくらいの大音量で奏でてきたのだ。結果万華鏡は誰も見たことがないような極彩色に仕上がる。覗いた人は初めて見る光景に驚き、その正体を知ろうと足を踏み入れていくうちに、自分が今どこにいるのかも分からなくなる。それこそが彼らの体現する「ドリーミー」であると思う。これが癖になる人は、どこまでも彼らのサウンドにひたりたくなる。僕もその一人なのだが。そのようにぶっとんだ夢の世界に誘ってくれる彼ら。もう1曲目「Secret For A Song」のイントロからその吸引力は抜群だ。ただ、これまでと若干違った印象を受けるのは、その万華鏡の作り方だ。理想とするものは変わらなくても、今作ではそこに迫るために今までとは違ったアプローチを多々試みている。特に5〜7曲目あたりの中盤の構成が魅力的だ。5曲目「Vermillion」の疾走感、艶っぽいギターに驚き、7曲目「In A Funny Way」はジョン・レノンのようにも聞こえる。コンパクトにまとめている分、メロディーにエッジが立っている。すごく新鮮に聞こえるのだ。このように新鮮な部分もあれば、いつものMercury Soundもあり、バラエティー豊かな作品となっている。これまでの過剰的なサイケデリアが後退したのは事実だが、聴き所の多さは半端ではない。そして結果的にはやはり見たことのない世界に僕らは連れて行かれるのだ。 おすすめ度★★★★☆(05/2/18) |
||||||
| Snowflake Midnight |
|
|
おすすめ度★★★★(21/10/08) |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
正直言うと、この手のバンドってたくさんいるが今ほとんどスルーしている。なんというか、こういうバンドの魅力ってどんな与太者でも、ひとたび楽器を手にしたらとてつもない光を放つというか、「ロックンロールしているときが幸せ」っていう強烈な表現衝動が感じられないと、魅力を感じないのだ。 雑多な音楽を上手く自分のロックンロールとして昇華できるバンドとして、今後も楽しみだ。そしてこういうセンスを持ったバンドにThe Ordinary
Boysというのがいたなぁと。彼らは今何をしているのかな? おすすめ度★★★★(09/27/08) |
||||||
|
||||||
 デンマーク出身のバンドだが、北欧というのは欧米に比べてきっと、表現の縛りが少ないのだと思う。自分たちが好きな音楽、好きなバンドのサウンドを自由にやることができるということで、北欧勢からは時々とんでもなく心のツボをついてくるバンドが現れる。昔スウェーデンにアトミック・スイングというバンドがいたが、彼らはまさにそうだ。まさに反則すれすれのメロディーとサウンド。残念ながら、欧米では評価が低くなりがちである。が、日本も割と北欧に似た自由な土壌があるので、どことなくシンパシーをおぼえるのだ。 デンマーク出身のバンドだが、北欧というのは欧米に比べてきっと、表現の縛りが少ないのだと思う。自分たちが好きな音楽、好きなバンドのサウンドを自由にやることができるということで、北欧勢からは時々とんでもなく心のツボをついてくるバンドが現れる。昔スウェーデンにアトミック・スイングというバンドがいたが、彼らはまさにそうだ。まさに反則すれすれのメロディーとサウンド。残念ながら、欧米では評価が低くなりがちである。が、日本も割と北欧に似た自由な土壌があるので、どことなくシンパシーをおぼえるのだ。MEWも僕にとってまさにそんなバンドである。きっとスマパン好きだろうと思っていたが、雑誌のインタービューではニルヴァーナやピクシーズなどの名前が挙がっていた。ただ、あえて近いものを挙げるとすればやはりスマパンを挙げずにはいられない。ドラムのバタバタ具合、ひたすら上り詰めていくギター、曲に戦慄を与えるストリングス、そしてヴォーカルの今にでも泣き叫んでしまいそうな感じはスマパンをどうしても連想してしまう。個人的にはスマパンが好きだったので、こういったテイストの音楽がまた聴けてうれしい限りである。ただ、メロディーはスマパンのようなメタルチックなものはなく、基本的に美しさと伸びやかさが同居したテイストのものが多い。非常に美しい曲が多い。また、この手の音楽のリスナーのツボもよく知っている。「Comforting Sounds」の最後のストリングスなどは、まさによだれものである。好き嫌いはありそうだが、良くできたアルバム。 おすすめ度★★★★(02.5.9) |
||||||
| And the Glass Handed Kites |
|
 Mew待望の2nd。デンマークという土地柄がそうさせるのか、1stではラウドながらトータルで見ると極上の美しさをたたえたサウンドを構築していた。ある種反則スレスレなところは北欧系の得意とするところ。今作でも、全曲が途切れずに流れていく、Munsun「Six」のようなアルバムをつくってくれた。思えばMunsunというバンドもギリギリまで「やりすぎる」という過剰性が売りだったわけだが、Mewにも同じような魅力を感じる。よくMuseに例えられているが僕はそうは思わない。Museの過剰性は「様式美」に向かっているが、MunsunやMewはもっとねじけたものである。 Mew待望の2nd。デンマークという土地柄がそうさせるのか、1stではラウドながらトータルで見ると極上の美しさをたたえたサウンドを構築していた。ある種反則スレスレなところは北欧系の得意とするところ。今作でも、全曲が途切れずに流れていく、Munsun「Six」のようなアルバムをつくってくれた。思えばMunsunというバンドもギリギリまで「やりすぎる」という過剰性が売りだったわけだが、Mewにも同じような魅力を感じる。よくMuseに例えられているが僕はそうは思わない。Museの過剰性は「様式美」に向かっているが、MunsunやMewはもっとねじけたものである。前作に比べるとその表現力は格段に進歩している。その中でもとりわけリズムの充実ぶりには目を見張るものがある。そして、前半重量級のナンバーが立て続けにくる流れはかなりよい。5曲目Apocalypsoまでの流れは最高だ。このようにヘヴィーなナンバーが若干増えたのは、そういったバンド自体の力量が上がってきている証なのだろう。 ただ、こういった変化はある種リスナーは読めてしまうところがある。なので、個人的にはもっと驚く変化をしてほしかったと思う。そして、「うーん、いいわぁー」と思わせるようなものを作ってほしかったとも思う。つまり、これだけのものを作れるバンドとして認識されていると思うのだ。どうも、Mando Diaoの「Hurricane Bar」とダブって見えてしまうんだよなぁ。悪いアルバムではないんだけどね。 おすすめ度★★★(05/10/5) |
|
|
||||||
|
おすすめ度★★★☆(08/5/26) |
||||||
|
||||||
 「チキン・ゾンビーズ」から、ミッシェルは常に「今これが最高」だという臨界点を常にドロップしてきたバンドである、ということはジャパンに腐るほど書かれているが、僕もおおむね同意見である。ただ、個人的には前作「ロデオ・タンデム・ビート・スペクター」で、そのような進化に一区切りがついたのではないかと思っていた。しかし今作は、その進化の歴史がさらに続いていくのかと思わせる素晴らしい内容になっている。1曲目「ブラック・ラブ・ホール」がかっこいい。上手い言葉が見つからないが、ジャズのインプロヴィゼーション的アプローチも試みながらのハードなナンバーである。 「チキン・ゾンビーズ」から、ミッシェルは常に「今これが最高」だという臨界点を常にドロップしてきたバンドである、ということはジャパンに腐るほど書かれているが、僕もおおむね同意見である。ただ、個人的には前作「ロデオ・タンデム・ビート・スペクター」で、そのような進化に一区切りがついたのではないかと思っていた。しかし今作は、その進化の歴史がさらに続いていくのかと思わせる素晴らしい内容になっている。1曲目「ブラック・ラブ・ホール」がかっこいい。上手い言葉が見つからないが、ジャズのインプロヴィゼーション的アプローチも試みながらのハードなナンバーである。シングルの「太陽をつかんでしまった」、「マリオン」(赤毛のケリーに似てるけど)などメロディアスなものから、「ブラッディー・パンキー・ビキニ」(ブランキーみたい)のような、語感で勝負するものまで、内容的には幅広くとっちらかった印象を受けるかもしれないが、最後のナンバー「NIGHT IS OVER」が来ることによって、きちっと完結した形となっている。この曲はアルバムの縦糸のような存在感がある。聴けばきっとわかっていただけると思う。 しかし、このバンドいったいどこまで行くつもりなのだろう。本当に信頼できるバンドである。 おすすめ度★★★★(02/3/21) Sabrina No Heaven  前作「Sabrina
Heaven」と同時期にレコーディングされながらも、ミニアルバムとして発表されたのはなぜだろう?聴く前はそんな疑問もあったのだが、聴いているうちにそういうことはどうでもよくなってきた。どの曲も本当に素晴らしい。速射砲のような攻撃的なナンバーから叙情的なナンバーまで、ここ近年で身につけた幅広さをここでもいかんなく発揮している。しかしながら、器用になったというのではなく、あくまでも表現者として生きていくことを選んだ上での冒険心がそうさせたのだと思う。そんな幅広さがありながら、今回も作品としては見事なまとまりがある。そして6曲というボリュームながら、フルアルバムを聴いているような、そんな満足感がある。 前作「Sabrina
Heaven」と同時期にレコーディングされながらも、ミニアルバムとして発表されたのはなぜだろう?聴く前はそんな疑問もあったのだが、聴いているうちにそういうことはどうでもよくなってきた。どの曲も本当に素晴らしい。速射砲のような攻撃的なナンバーから叙情的なナンバーまで、ここ近年で身につけた幅広さをここでもいかんなく発揮している。しかしながら、器用になったというのではなく、あくまでも表現者として生きていくことを選んだ上での冒険心がそうさせたのだと思う。そんな幅広さがありながら、今回も作品としては見事なまとまりがある。そして6曲というボリュームながら、フルアルバムを聴いているような、そんな満足感がある。とにかく、今のミッシェルの充実ぶりが感じ取れるアルバムであると思う。いやー、ライブが観たいなぁ。 おすすめ度★★★★(03/8/8) |
||||||
|
||||||
 The
Wonder Stuffのフロントマン、マイルス・ハントの新バンドのファーストアルバム。WS解散後は、あまり熱心に追いかけてはいなかったのだが、このマイルス・ハントという男の一本筋が通っているというか、音楽に関しては一切妥協を許さない姿勢に、常にリスぺクトだけはしてきた。解散後結成したVent414はあまり僕好みではなかったのだが、今回のアルバムは彼のソングライティング能力がいかんなく発揮されていて、魅力を持ったアルバムに仕上がっている。 The
Wonder Stuffのフロントマン、マイルス・ハントの新バンドのファーストアルバム。WS解散後は、あまり熱心に追いかけてはいなかったのだが、このマイルス・ハントという男の一本筋が通っているというか、音楽に関しては一切妥協を許さない姿勢に、常にリスぺクトだけはしてきた。解散後結成したVent414はあまり僕好みではなかったのだが、今回のアルバムは彼のソングライティング能力がいかんなく発揮されていて、魅力を持ったアルバムに仕上がっている。サウンド的にはWSの面影はなく、基本的にメロディーをストレートにシンプルに鳴らそうとする彼らの意志が感じられる。以前の作品では、期待をいい意味でとことん裏切り続けるようなアイディアが満載であったが、今回はその断片すら残っていない。驚くほど正直に自分をさらけ出しているという感じがする。どっちが素のマイルスかといったらきっとこっちなのだろう。ライブで、かのWater boysの「Fisherman's Blues」をカバーしているあたりからもその志向は伺えた。「モダン・イディオット」が出てからほぼ10年。やっとマイルスはスタート地点に立ったのかもしれない。個人的にはどうしてもWSで見せたようなロックの臨界点をもう一度体験させてほしいのだが、それを望むのは野暮といったものだ。 おすすめ度★★★☆(02/5/23) |
||||||
|
||||||
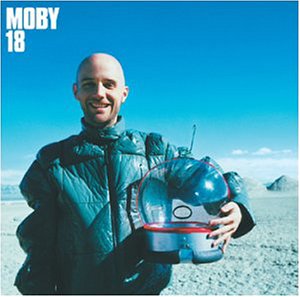 今までMobyというと「テクノ」というイメージが強く、僕はここ近年のテクノにあまり興味がなかったので、聴いたこともなかった。大ヒットした「プレイ」さえも聴いていない。つまり「18」が初体験である。というよりは、MTVで「We
Are All Made Of The
Stars」は何回も見ていた。この曲を「ダサい」「恥ずかしい」といっている人もいるようだが、僕には何か心に響くものを感じた。すごく好きというのともちょっと違う。とにかくMobyの作る音楽が気になるようになったのだ。そこで「18」を聴いてみたのだが、見事にはまってしまった。 今までMobyというと「テクノ」というイメージが強く、僕はここ近年のテクノにあまり興味がなかったので、聴いたこともなかった。大ヒットした「プレイ」さえも聴いていない。つまり「18」が初体験である。というよりは、MTVで「We
Are All Made Of The
Stars」は何回も見ていた。この曲を「ダサい」「恥ずかしい」といっている人もいるようだが、僕には何か心に響くものを感じた。すごく好きというのともちょっと違う。とにかくMobyの作る音楽が気になるようになったのだ。そこで「18」を聴いてみたのだが、見事にはまってしまった。非常にエモーショナルな作品である。曲的にはバラエティに富んでいて、ロック、ポップ、ゴスペル、ソウルなどいろいろな音楽の要素が詰まっているのだが、それらがきちっとMobyの手によって調理されている。これだけバラバラでありながらも、なにか一本筋の通ったような作品である。Mobyはメッセージを持った職人であるということを感じさせられる。女性ヴォーカルの曲も多いが、いいメロディーが多いので聴けてしまう。曲数が多くても最後まですんなりと聴けてしまう佳作である。 おすすめ度★★★★(02/5/14)
|
||||||
|
||||||
 Mogwai,6枚目のアルバム。これぞポストロックという佇まいから少しずつ音楽性の幅を広げてきた彼ら。ここ最近を見ると、以前のイメージから変わろうとあれこれ試行錯誤しているところがあり、そこが作品の出来を左右していた。ゆえに「もう少しシンプルに考えると素晴らしくなるのになぁ」という思いを抱いていた。 Mogwai,6枚目のアルバム。これぞポストロックという佇まいから少しずつ音楽性の幅を広げてきた彼ら。ここ最近を見ると、以前のイメージから変わろうとあれこれ試行錯誤しているところがあり、そこが作品の出来を左右していた。ゆえに「もう少しシンプルに考えると素晴らしくなるのになぁ」という思いを抱いていた。 それはよくある、表現者と聴き手の欲求のズレの部分なのだろう。例えばTravisがラウドになってしまうことへの寂しさと似ていて、昔からのファンはどうしてもこれまでのイメージを求めてしまう。それでもMogwaiはまだ上手く折り合いをつけていたほうだと思う。変化し続けながらも、本来の魅力はそのまま維持し続けてきた。それは「夢と現実の狭間をたゆたうようなメロディーライン」だ。 |
||||||
|
||||||
 最近知ったMojave3というバンド。なんと元スロウダイヴ。あのシューゲイザー一派なわけですが、音楽的にこのMojave3はかなり気持ちいい方へいっちゃっています。どこにもギターノイズはございません。ウェストコーストロックのような曲があったり、どう聞いてもボブ・ディランの「Like
A Rolling
Stone」だったり、かなりサウンド的にはアメリカっぽいです。とても元クリエイションのバンドだったとは思えません。メロディーもそこそこにキャッチーで、全体的にはドリーミーな感触を持ったサウンドといってよいでしょう。個人的にはメロディーはスロウダイヴ時代も結構こういった甘いメロディーがあったと思うんですが、まるっきり表現方法が変わってしまったなと思います。オルガンの使い方などすごくうまいなと思うのですが、スロウダイヴのようには頭に残っていかないなという印象を受けます。特に前半の心地よさが、後半になるとやや単調になってしまい、何か気がつけば終わっているという感じがします。メロディーの美しさやサウンドセンスなどは光るものがありますが、もう一歩頭に残るものが欲しいような気がします。もったいない。もうギターノイズは彼らの頭にはないのかな。もう一工夫があれば、もっと人気が出るような。 最近知ったMojave3というバンド。なんと元スロウダイヴ。あのシューゲイザー一派なわけですが、音楽的にこのMojave3はかなり気持ちいい方へいっちゃっています。どこにもギターノイズはございません。ウェストコーストロックのような曲があったり、どう聞いてもボブ・ディランの「Like
A Rolling
Stone」だったり、かなりサウンド的にはアメリカっぽいです。とても元クリエイションのバンドだったとは思えません。メロディーもそこそこにキャッチーで、全体的にはドリーミーな感触を持ったサウンドといってよいでしょう。個人的にはメロディーはスロウダイヴ時代も結構こういった甘いメロディーがあったと思うんですが、まるっきり表現方法が変わってしまったなと思います。オルガンの使い方などすごくうまいなと思うのですが、スロウダイヴのようには頭に残っていかないなという印象を受けます。特に前半の心地よさが、後半になるとやや単調になってしまい、何か気がつけば終わっているという感じがします。メロディーの美しさやサウンドセンスなどは光るものがありますが、もう一歩頭に残るものが欲しいような気がします。もったいない。もうギターノイズは彼らの頭にはないのかな。もう一工夫があれば、もっと人気が出るような。おすすめ度★★★(04/3/7)いる |
||||||
|
||||||
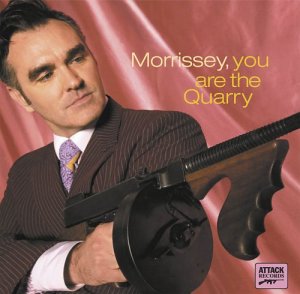 モリッシーが還ってきた。 モリッシーが還ってきた。1曲目「America Is Not The World」もうタイトルからしてモリッシーぽいが、とにかく最初からモリッシー節が全開である。そして2曲目のシングル「Irish Blood,English Heart」、これがが破格の出来である。これまでのソロ作の中でも1,2を争うほどの攻撃性を持ったナンバーだ。スミスが好きでも、ソロはちょっと・・・という人でも気に入ると思う。その後は、ミディアム〜スローなナンバーが続き、前作「マルアジャステッド」のようにゆるく進んでいくのかなと思いきや、アルバムの後半からまたアグレッシヴさが復活。もうひとつまとめきれていないかなーという印象もあるが、「First Of The Gang To Die」なんかは、シングアロングナンバーで、あまりのポップさにびっくり。そして、モリッシーの伸びやかなヴォーカルと相性の良い曲が続く。この辺はさすがである。 ただ、アルバムを全体的に見るといいメロディーながら、そのまとめ方やアレンジの部分でもう一工夫できたんじゃないかというのが数曲あった。いいアルバムであるのは間違いないのだけど、完璧とは言えない甘さが見られた。まぁ、これはプロデューサーであるジェリー・フィンの色が強く出ているのだと思うので、単に自分の好みでなかったということかもしれない。つまりは僕はどうしても、ジョニーの影や、スミス的なるものを求めてしまうのだ。リフ一つ一つが気になる。こればかりは本当にもうどうしようもないのである。病気だ。 しかしながら、世の中にはもう「存在するだけでいい」という人間がいる。今の日本人にとっては長嶋茂雄もそうなのだと思う。車いすでも、話ができなくても世間は彼のユニフォーム姿を望んでいる人でいっぱいだろう。僕にとっては、モリッシーがそうだ。モリッシーには失礼かもしれないが、彼が歌い続ける限り、僕はずっと追いかけると思う。 おすすめ度★★★★(04/6/7) |
||||||
| Live at Earls Court |
|
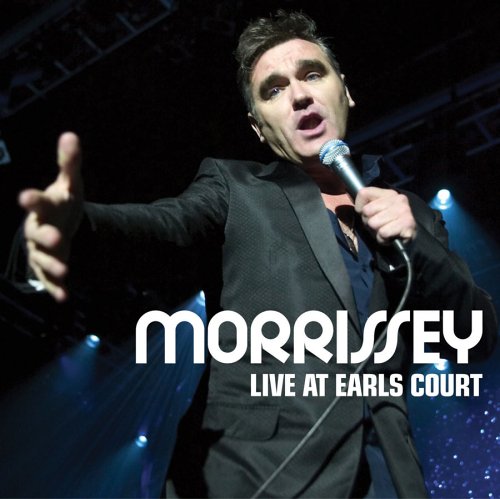 「元気モリモリ」・・・そんなくだらないダジャレが思わず浮かんでしまうほど、今のモリ様のいい状態が伝わってくるライヴ盤である。1曲目の「How
Soon Is Now?」は演奏はダメダメなんだけど、モリ様の歌はかつて無いほどに艶っぽくなっている。この年で歌の技術が向上しているのもある意味凄いです。このほかにもいくつかスミスナンバーが聴けるのが今作の売りだとは思うが、正直曲によって演奏のばらつきがある。「Bigmoth
Strikes Again」は途中のギター、ドラムがショボイし、「There Is A Light〜」は遅すぎて・・・。逆に良かったのは「Shoplifters〜」。これはなかなかいい味を出していた。 「元気モリモリ」・・・そんなくだらないダジャレが思わず浮かんでしまうほど、今のモリ様のいい状態が伝わってくるライヴ盤である。1曲目の「How
Soon Is Now?」は演奏はダメダメなんだけど、モリ様の歌はかつて無いほどに艶っぽくなっている。この年で歌の技術が向上しているのもある意味凄いです。このほかにもいくつかスミスナンバーが聴けるのが今作の売りだとは思うが、正直曲によって演奏のばらつきがある。「Bigmoth
Strikes Again」は途中のギター、ドラムがショボイし、「There Is A Light〜」は遅すぎて・・・。逆に良かったのは「Shoplifters〜」。これはなかなかいい味を出していた。ただこのアルバムのいいところはこれだけスミスナンバーが入っていながらも、あくまで主役はソロナンバーであることだ。新旧織り交ぜてあるが、スミスナンバーと比べても遜色がない。というよりはバンドとしてもそちらの方が相性がいい。Morrisseyのバンドは昔から下手なことが多かったので演奏は期待していないが、ソロ曲でのヨタヨタぶりは最早このバンドの「グルーヴ」と化しつつある。 それでも、このライヴ盤が素晴らしいと感じるのは、Morrisseyが今でも聴き手の心に「Shoplift」を仕掛けてくる、あのMorrisseyであるということがこのライヴから凄く伝わってくるからだ。Morrisseyがステージに上がってきた客を抱きしめるというのは、パフォーマンスではなく、そこで「約束」を交わしているのではないかと思う。それは、かつてSmithsの曲を聴いて自殺したファンに「僕らの曲が死のそばにあったことは、幸せなことだ」と言ったことが証明するように、「あなたが死ぬときには僕がそばにいるよ。それが僕に出来る唯一のことで、あなたにとって幸せなことなんだ」というものなのだと思う。それはもう半ば強引なもので、自分自身の心を彼にスッとかすめ取られるようなものだ。あなたの人生がどんなものであっても、最後には僕(Morrissey)がいる。Morrisseyはそのことを歌いたいのだし、これからも歌い続けるだろう。このライヴ盤での彼の幸せそうな声、観客の興奮を耳にするにつけ、僕はそう思う。 自分の存在が、人の人生を揺さぶり、そして死にさえ直面するということ。そういった宿命を信じ、全うしようとすること。それは、Morrisseyにとっては,「健全」な思想であると思う。 おすすめ度★★★★(05/5/14) |
|
| Years Of Refusal |
|
|
|
|
|
||||||
 僕は「Light,Slight,Dummy」が初体験で、とにかくひたすら限界を出し続けるペース全く無視のサウンドは非常に面白くしかもかっこよかった。こういったものが、日本でもごく自然に認知されるようになって、評価されるようになったと言うことも印象的であった。僕の中では今でもモーサムのイメージは「Light,Slight,Dummy」である。崖っぷちをおそれることなく全力疾走でどこまでも走っていくようなそんな感じである。 僕は「Light,Slight,Dummy」が初体験で、とにかくひたすら限界を出し続けるペース全く無視のサウンドは非常に面白くしかもかっこよかった。こういったものが、日本でもごく自然に認知されるようになって、評価されるようになったと言うことも印象的であった。僕の中では今でもモーサムのイメージは「Light,Slight,Dummy」である。崖っぷちをおそれることなく全力疾走でどこまでも走っていくようなそんな感じである。しかし、このアルバムは全く違うアプローチから作られている。1曲目、静かなシンセ音から始まる。しかし、徐々に機械的なブレイクビーツが絡んできてこれから始まるものを予感させる。そして、次の「Hang Song」で繰り広げられる都市的なサウンドは今までにはなかったものだ。中にはモーサムの真骨頂というべきパンキッシュな轟音ナンバーもあるが、全体的にはエレクトロを駆使したミディアム・スローなナンバーが多い。面食らったファンが多かったと聞くが、個人的には全くすんなりと受け入れられた。上手くは言えないのだが、これは彼らにとっての「KID A」なのではないかと思う。音楽を創り出そうとするのではなく、彼ら頭の中にある音・言葉=脳内ミュージックをそのまま形に表したようなものなのではないかと思う。だから、全く不自然さを感じなかった。そして、これまでの作品よりも彼らの言葉の魅力はより伝わるようになったと思う。「go around my head」「endless D」なんか最高だ。是非聞いて欲しい。 穏やかながら、そこから染み出る毒は強烈だ。毒に当たるか、それともその毒でトリップすることができるか。聴き手次第の強烈な作品を作ってくれたもんだ。やるね。 おすすめ度★★★★☆(04/5/16) |
||||||
| ペチカ |
|
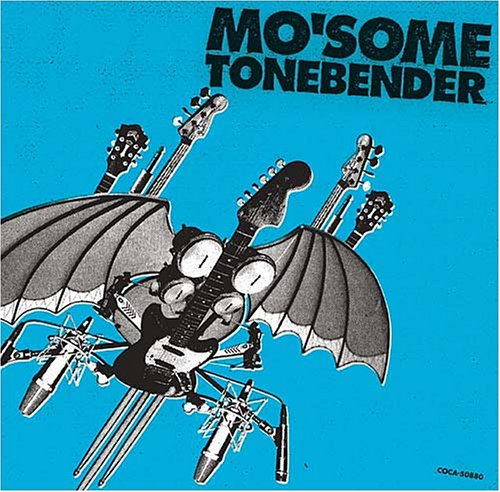 モーサム珠玉のミディアムナンバー。間違いなくバンドを代表する1曲になるだろうし、これほどに切ない曲はこれまで無かっただろう。じゃあどう切ないかというと、これが徹頭徹尾切ない。「凡人のロックンロール」も切なかったが、「ペチカ」は更に深いところをえぐり出すようなそんな力がある。 モーサム珠玉のミディアムナンバー。間違いなくバンドを代表する1曲になるだろうし、これほどに切ない曲はこれまで無かっただろう。じゃあどう切ないかというと、これが徹頭徹尾切ない。「凡人のロックンロール」も切なかったが、「ペチカ」は更に深いところをえぐり出すようなそんな力がある。「少しずつ 空が光を取り戻し始める頃 たった今届いたばかりの新聞を広げたんだ」 とりとめもない朝の日常と言い切ることは出来るだろう。しかし、ひろげた新聞の上で起こる出来事は日常に潜む「非日常」だ。自分にとってリアルなこと。それは紛れもなく静かな朝を迎えることであり、「今日が特別な一日になれば」という儚い期待だ。それは世界がどう動こうとも、少しずつ終焉の時を迎えつつあっても、その思いは変わらない。そういった「永遠なるもの」がこの曲からは感じられる。 サウンド面では、「The Story Of Adventure」以降の独特のポップ感に更に磨きがかかった感じだ。「ペチカ」の中盤のギターソロは向井秀徳の言うとおりハートを掻きむしられるような狂おしさがある。そういったフレーズ(ややベタベタな感じ)はこれまで「御法度」なのではないかと思っていたのだが、この曲では開き直ったかのようにそういった縛りを解放しているようだ。カップリングの「Good Trip ?Bad Trip?」「ダミアン」はいつもの爆裂ナンバーであるが、メロディーが驚くほどキャッチーだ。それ故、どの曲も大変耳に残る。カップリングはアルバムには収録されないが、されていてもおかしくないほど完成度は高い。 ただ、それでもやはり「ペチカ」のインパクトは群を抜いている。「モーサムが贈るこの冬最高の優しいうた」というキャッチコピーがつけられているが、それは確かにそう思う。でも、自分にはその「優しさ」を享受できるのだろうか、ということを考えると逆に切なくなってしまうのだ。 おすすめ度★★★★☆(05/11/12) |
|
| Sing! |
|
|
それでも、後半になると「ひまつぶしpt2」「グッモーニン」「虹を架けて」「JOY」といった持ち味を発揮した曲が増えてきて、少し安心する。それでも物足りないのは確か。 3ピースバンドという最小構成が見せるギリギリのテンションって、やっぱりすごいなと思うことがよくある。例えばBlankey Jet
City。誰も入り込めない背筋の凍り付くような世界観。そういうものを見せられるバンドって少ないと思う。そして、モーサムはそこへと聴き手を誘ってくれるバンドであることは間違いない。もう一度、頼む! おすすめ度★★★(10/11/08) |
|
|
||||||
 「音がGrandaddyっぽい」という評判を聞きつけて、なにげに買ったのだがなかなかよかった。正直Grandaddyよりはメロディーに深みがない印象を受けたが、シンセのチープ感の出し方がダサかっこよく、エレポップが好きな人にも広く受け入れられそうなサウンドである。とくにM-2が秀逸。おもちゃ箱を開けたようなポップ小品集。 「音がGrandaddyっぽい」という評判を聞きつけて、なにげに買ったのだがなかなかよかった。正直Grandaddyよりはメロディーに深みがない印象を受けたが、シンセのチープ感の出し方がダサかっこよく、エレポップが好きな人にも広く受け入れられそうなサウンドである。とくにM-2が秀逸。おもちゃ箱を開けたようなポップ小品集。おすすめ度★★★☆(02/4/20) |
||||||
|
||||||
 個人的なことをいうと、Museというのは非常に「びみょー」なバンドである。1st「Showbiz」は、とてもデビューアルバムとは思えないくらい良くできたアルバムであった。キャッチーな曲を挟みながらも、怒濤の世界へとリスナーを誘っていく展開は、非常につぼを押さえているなと思わせ、そこが新人らしからぬ感じがしたのだ。しかしながら、アルバムの後半へいくとちょっとした「胸焼け状態」になる。世界が濃密故に少し「遊び」なんぞもほしいなと思うのだ。2ndアルバムにも同様のことが言えた。ただ、1曲1曲は本当にすばらしく、マシュー・ベラミーのソングライティング能力というのはとても高いレベルにあることは間違いない。なので、これまでの付き合いは、シングル単位でというのが僕とMuseの関係であった。 個人的なことをいうと、Museというのは非常に「びみょー」なバンドである。1st「Showbiz」は、とてもデビューアルバムとは思えないくらい良くできたアルバムであった。キャッチーな曲を挟みながらも、怒濤の世界へとリスナーを誘っていく展開は、非常につぼを押さえているなと思わせ、そこが新人らしからぬ感じがしたのだ。しかしながら、アルバムの後半へいくとちょっとした「胸焼け状態」になる。世界が濃密故に少し「遊び」なんぞもほしいなと思うのだ。2ndアルバムにも同様のことが言えた。ただ、1曲1曲は本当にすばらしく、マシュー・ベラミーのソングライティング能力というのはとても高いレベルにあることは間違いない。なので、これまでの付き合いは、シングル単位でというのが僕とMuseの関係であった。さて、3rdではどうなのだろうかと不安混じりに聴いてみたのですが、はっきり言いましょう。最高傑作です。何がどう変わったのかは、はっきり説明できないけど、最後まで集中して聴けてしまいます。しかも、また繰り返し聞きたくなります。曲の良さは相変わらず、トーンは世界情勢に影響されている部分もあり、やや暗いのですが、今回は曲の構成がすごくバランスがよいので、最後まで引きつけられます。また、バンドのグルーヴも以前に比べて強固になっているのも、すばらしいところです。UKロックが好きで本当に良かったと思わせてくれる1枚です。 おすすめ度★★★★★(03/11/24) |
||||||
| HAARP |
|
|
おすすめ度★★★★☆(4/23/08) Time Is Running Out
|
|
|
||||||
 あちらこちらで高評価を受けているTHE MUSIC。バンド固有のグルーヴという点で、ローゼズなどとも比較されている。ただ、これはちょっと違うような気がする。確かにシングルはどれもキラー・チューンともいうべき即効性のあるメロディーと熱っぽいグルーヴが特徴的である。が、グルーヴに関して個人的にはあまり新鮮な感じはしなかった。サウンド以上に佇まいに魅力を感じるバンドだと思う。「The
People」のPVなどはまさに彼らの雰囲気を見事に体現している。ヴォーカルの歌い回しはどことなく、60後期〜70年代のハードロックのようだ(僕はあまり得意ではないが)。 あちらこちらで高評価を受けているTHE MUSIC。バンド固有のグルーヴという点で、ローゼズなどとも比較されている。ただ、これはちょっと違うような気がする。確かにシングルはどれもキラー・チューンともいうべき即効性のあるメロディーと熱っぽいグルーヴが特徴的である。が、グルーヴに関して個人的にはあまり新鮮な感じはしなかった。サウンド以上に佇まいに魅力を感じるバンドだと思う。「The
People」のPVなどはまさに彼らの雰囲気を見事に体現している。ヴォーカルの歌い回しはどことなく、60後期〜70年代のハードロックのようだ(僕はあまり得意ではないが)。シングル以外の曲もメロディーがよく、全体的にはよくまとまったアルバムだと思う。ただ、ちょっと冗長に感じられるところもあるので、その点あたりを次回作で解消してもらいたい。才能はあるのだから、きっと可能だろう。 おすすめ度★★★☆(02/9/16)
|
||||||
|
||||||
 最近、この「オルタナ・カントリー」というジャンルが気になる今日この頃。でも、このMy Morning Jacketの新作には確かにカントリーっぽいチューンもあるが、全体を覆っているのはフレミング・リップスやマーキュリー・レヴを想起させるような、甘美なサイケデリアだ。失礼な言い方だが、音楽的なバックボーンとしては少々オヤジくさい所がある。王道のアメリカン・ロックのテイストがかなり感じられるのだが、彼らがそれだけで終わっていないのは、アメリカン・ロックが決して健康的なものではなく、もっと「ヒリヒリとしたもの」ということを正しく認識しているからだ。Beckは古典的に捉えられがちであるアメリカのフォークやカントリーといった音楽が伝える心の痛みや閉塞感は現代でも瑞々しく、表現として有効であるということを自身の作品でしっかりと証明している。優れた表現者は、同時に優れた理解者でもある。そういう意味で、彼らも素晴らしい表現者であり、理解者であるのだろう。このアルバムから伝わってくる、孤独感や寂寥感は本当に生々しい。人間の本質に鋭く迫っているのが、音から感じられる。 最近、この「オルタナ・カントリー」というジャンルが気になる今日この頃。でも、このMy Morning Jacketの新作には確かにカントリーっぽいチューンもあるが、全体を覆っているのはフレミング・リップスやマーキュリー・レヴを想起させるような、甘美なサイケデリアだ。失礼な言い方だが、音楽的なバックボーンとしては少々オヤジくさい所がある。王道のアメリカン・ロックのテイストがかなり感じられるのだが、彼らがそれだけで終わっていないのは、アメリカン・ロックが決して健康的なものではなく、もっと「ヒリヒリとしたもの」ということを正しく認識しているからだ。Beckは古典的に捉えられがちであるアメリカのフォークやカントリーといった音楽が伝える心の痛みや閉塞感は現代でも瑞々しく、表現として有効であるということを自身の作品でしっかりと証明している。優れた表現者は、同時に優れた理解者でもある。そういう意味で、彼らも素晴らしい表現者であり、理解者であるのだろう。このアルバムから伝わってくる、孤独感や寂寥感は本当に生々しい。人間の本質に鋭く迫っているのが、音から感じられる。そしてこの自在なメロディー、振幅の激しい展開、非常に中毒性の高い作品に仕上がっていると思う。前述のバンドが好きな人たちにとっては決して嫌いな音ではないと思う。轟音系サイケとしては物足りないかもしれないが、Beach Boysの「Friends」にも似た、儚く美しいガラスのような世界が展開されている。、フジロックで見とけばよかった(激しく後悔)。 おすすめ度★★★★☆(05/10/29) |
||||||
|
||||||
 Mystery Jetsのセカンド。ファースト「Making
Dens」は当時よく聞いたし、ポップなメロディーと骨太でありながらちょっとひねたサウンド・プロダクションがとても好みな感じであった。 Mystery Jetsのセカンド。ファースト「Making
Dens」は当時よく聞いたし、ポップなメロディーと骨太でありながらちょっとひねたサウンド・プロダクションがとても好みな感じであった。そして、このセカンドであるが、1曲目「Hideaway」がかかった瞬間、頭の中に「?」がたくさん浮かんできた。「あれっ、間違ったか?」と確かめたくなるくらいに。 極めつけは「Two Doors Down」。このイントロのドラム、シンセの音色、絶対80'sですよ。Duran Duran、スパンダー・バレエあたりにこんな曲なかったか?カジャ・グーグーとか、そういえばトンプソン・ツインズ好きだったなぁ。R35サウンドとでも言えそうな1曲です。 80年代のダンサブルなポップ・バンドのような音作り。全体的に言うと、ネオ・サイケ的な要素はかなり後退し、代わりにタイトなビート感を強調した曲が多くなっている。今回はエロール・アルカンのプロデュースということで、ある程度ダンサブルな方へ傾くことは予測されたけど、エロールが手がけた作品の中でも、かなりライトな感じではないだろうか? 前作のような、無骨さやフォーキーなテイストが絡んだサウンドがないのは正直残念。しかしながら、彼らの書くメロディーはどちらかというと今作の方がよりクリアに伝わってくる。つまり相性はこういうポップなアレンジの方がいいのだろう。最初は面食らった自分も、最近はすっかりこのサウンドになじんできている。 おすすめ度★★★★(08/5/24) |
||||||
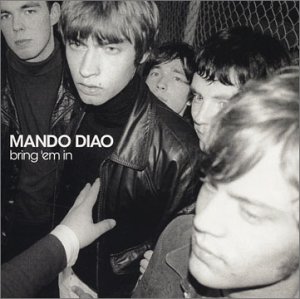 かなり前から話題になっていたが、8月にやっと購入。未だにハマリ続けております。ストロークス、リバティーンズなど新世代のロックン・ロールがここのところずーっとシーンを賑わしている。複雑になりすぎた感のあるロックシーンから、こうしたシンプルかつプリミティブな魅力を持ったバンドがゾクゾクと出てくるのはある意味、自然な流れだったと思う。こういった流れは、きっと今後も繰り返されていくだろう。ただ、その中で人々にインパクトのある作品を残していくというのは実に難しい。セールスの問題ではない。どんなに世の中が変わっていっても、変わらぬ魅力を持った作品を生み出すというのは、ロックが時代性に左右されがちなものだけに難しいと思う。
かなり前から話題になっていたが、8月にやっと購入。未だにハマリ続けております。ストロークス、リバティーンズなど新世代のロックン・ロールがここのところずーっとシーンを賑わしている。複雑になりすぎた感のあるロックシーンから、こうしたシンプルかつプリミティブな魅力を持ったバンドがゾクゾクと出てくるのはある意味、自然な流れだったと思う。こういった流れは、きっと今後も繰り返されていくだろう。ただ、その中で人々にインパクトのある作品を残していくというのは実に難しい。セールスの問題ではない。どんなに世の中が変わっていっても、変わらぬ魅力を持った作品を生み出すというのは、ロックが時代性に左右されがちなものだけに難しいと思う。 1st,「Bring Em
In」はかなり衝撃的なアルバムでした。エネルギーに満ちあふれているというか、あるコピーを借りるとすれば「俺は今、ロックがやりてぇのだ!!」状態である。それぐらい、ロックという音楽に自分のありったけの想いをぶつけたとんでもないアルバムであった。そういう意味では、初期ビートルズのピュアさと引けをとらないくらいの美しさがあった。「Sheepdog」も「The
Band」も本当にまばゆくて、最高に格好良かった。
1st,「Bring Em
In」はかなり衝撃的なアルバムでした。エネルギーに満ちあふれているというか、あるコピーを借りるとすれば「俺は今、ロックがやりてぇのだ!!」状態である。それぐらい、ロックという音楽に自分のありったけの想いをぶつけたとんでもないアルバムであった。そういう意味では、初期ビートルズのピュアさと引けをとらないくらいの美しさがあった。「Sheepdog」も「The
Band」も本当にまばゆくて、最高に格好良かった。



 僕がMobyを熱心に聞くようになったのは前作「18」がリリースされてからである。それはMobyがより強い表現を求めて、歌詞入りの曲を大幅に増やしたアルバムであり、そのスピリチュアルな佇まいにいたく感動したからである。しかし、この「Hotel」を聴くと「18」はまだ序章に過ぎないという気持ちになってくる。
僕がMobyを熱心に聞くようになったのは前作「18」がリリースされてからである。それはMobyがより強い表現を求めて、歌詞入りの曲を大幅に増やしたアルバムであり、そのスピリチュアルな佇まいにいたく感動したからである。しかし、この「Hotel」を聴くと「18」はまだ序章に過ぎないという気持ちになってくる。

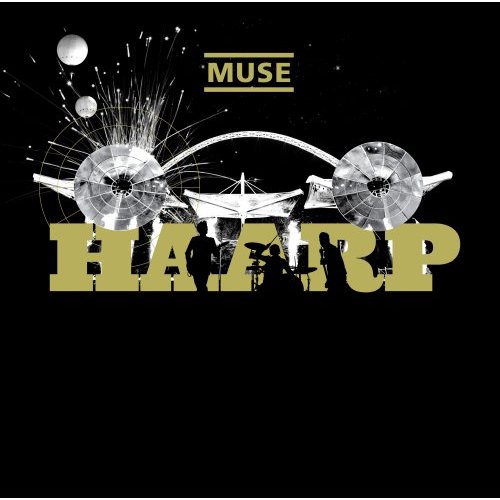 サマソニ06で見た、2度目のMUSE。始めて見た2000年と比べると、もう別のバンドかと思うくらい。元々スケールの大きさを感じさせるバンドであったが、それからどんどん大きくなり今や得体の知れない強大なパワーを持ったバンドへと変貌した。ただただ圧倒されたことを覚えている
サマソニ06で見た、2度目のMUSE。始めて見た2000年と比べると、もう別のバンドかと思うくらい。元々スケールの大きさを感じさせるバンドであったが、それからどんどん大きくなり今や得体の知れない強大なパワーを持ったバンドへと変貌した。ただただ圧倒されたことを覚えている 前作はメロディーとグルーヴの質感が見事にマッチした素晴らしいサウンドながら、ヴォーカルの癖や所々でお腹いっぱいになる感じがイマイチ好きになれなかったりして、その、微妙な作品であった。今作は、ヴォーカルの癖はまんま変わらないものの、1曲1曲がよく練られている。とはいえメロディー的には前作の方が王道で即効性があったとは思うが、構成上の強弱の付け方が憎らしいほど上手い。前作のひたすら熱くなる感じはなくて、曲によってひたひたと迫ってきたり、いい加減じらしたところで一気に解放するなど、多様性を身につけたように感じる。きっと彼ら自身が様々なことを表現したくなって、それに見合う表現力を身につけたと言うことなのだと思う。というくらいサウンドのはまり具合が見事だ。聴けば聴くほど深まっていくアルバムだと思う。
前作はメロディーとグルーヴの質感が見事にマッチした素晴らしいサウンドながら、ヴォーカルの癖や所々でお腹いっぱいになる感じがイマイチ好きになれなかったりして、その、微妙な作品であった。今作は、ヴォーカルの癖はまんま変わらないものの、1曲1曲がよく練られている。とはいえメロディー的には前作の方が王道で即効性があったとは思うが、構成上の強弱の付け方が憎らしいほど上手い。前作のひたすら熱くなる感じはなくて、曲によってひたひたと迫ってきたり、いい加減じらしたところで一気に解放するなど、多様性を身につけたように感じる。きっと彼ら自身が様々なことを表現したくなって、それに見合う表現力を身につけたと言うことなのだと思う。というくらいサウンドのはまり具合が見事だ。聴けば聴くほど深まっていくアルバムだと思う。