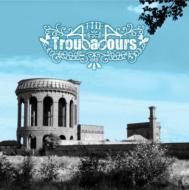Review T -
|
||||||
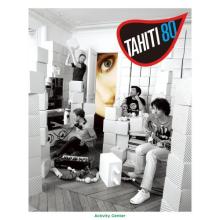 Tahiti80の新作。最近ソロ活動がメインとなっていたグザヴィエであるが、そこである程度自分の実験性を放出したのか、このアルバムでは実にシンプルなアプローチをしているなという印象を受ける。 Tahiti80の新作。最近ソロ活動がメインとなっていたグザヴィエであるが、そこである程度自分の実験性を放出したのか、このアルバムでは実にシンプルなアプローチをしているなという印象を受ける。雑誌なんかでは「ロック色が強い」ようなことが書かれていたが、さほどロックな感じはしない。どちらかいうと全体的にざっくりとした風通しの良いポップで構成されている。 このバンドにおいては、キャッチーでポップなメロディラインはもう当たり前のこと。ただ、これまで売りでもあった特徴的なシュガーコーティングはほどほどにして、素材の良さで勝負しようという今回のプロデュースは成功だと思う。ともすれば近作で感じられた過剰な甘さがとれたように思う。もちろんこれは好みの問題であるが、個人的にはこれくらいすっきりしている方が、このバンドの本質や良さが伝わるのではないかと思う。 ただ、これはジレンマであるが、その「すっきりさ」のために、強烈に耳に残る感じはやや後退した。いい曲揃いなのだが、聴き終えたあとにどことなく物足りなさがあるのも確か。あまりに淀みなくスマートなので、アルバムの流れに変化をつけるなど、そういう工夫があればなと思うところもある。 それでも、バンドの高いポテンシャルを十分に感じられるアルバムである。今のサウンドにポップの毒気が加われば無敵だろう。それは次への楽しみにとっておこうと思う。 おすすめ度★★★☆(18/10/08) |
||||||
|
||||||
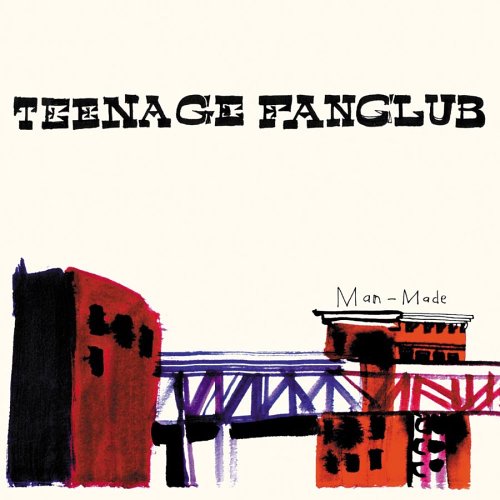 常に待ち焦がれてしまうTFCの新作。彼らは不思議なバンドで、初期の頃よりも円熟期とも言える現在の方が果敢に実験的な音楽にトライしているように見える。傑作「Grandprix」「Songs
From Northern Britain」の頃はインタービューでも、「斬新さや奇抜さを求めるのではなく、単純にいい音楽を作りたい」という発言をしていたように記憶している。しかし、前作「Howdy!」あたりから彼らは「斬新・奇抜」とまでは行かなくても、明らかに「Something
New」を求めているように感じる。 常に待ち焦がれてしまうTFCの新作。彼らは不思議なバンドで、初期の頃よりも円熟期とも言える現在の方が果敢に実験的な音楽にトライしているように見える。傑作「Grandprix」「Songs
From Northern Britain」の頃はインタービューでも、「斬新さや奇抜さを求めるのではなく、単純にいい音楽を作りたい」という発言をしていたように記憶している。しかし、前作「Howdy!」あたりから彼らは「斬新・奇抜」とまでは行かなくても、明らかに「Something
New」を求めているように感じる。今作のプロデューサーはトータスのジョン・マッケンタイア。ここでジョンはおそらく彼らが望んだであろう仕事をきっちりとこなしている。シカゴ音響系の財産を彼らのメロディーとの相性を考えながら、絶妙なチョイスで取り込んでいる。個人的に最初聴いたときは彼らの売りでもあるザックリしたギターが全然なく、やけにアメリカ的なドライさが耳について物足りなさを感じたのだが、よくよく聴くと今作ではそのギターサウンドのはいる余地があまりないことに気づいた。つまりこのサウンドは、ジョン・マッケンタイアの趣味というよりは、今回の彼らの書いたメロディーがもたらした必然なのだろう。ノーマン、ジェリー、レイモンドの3人は今までも多くの名曲を生み出し今作でも素晴らしい質を保っているが、自分たちの癖に頼って曲を書くのではなく、それぞれが常に新しい形を求めているように思う。それが今回サウンド面の変化にがっちりはまっている。見事だ。まだ当分彼らの新作が届くのを楽しみに待てそうだ。「Man-Made」を聴きながら。 おすすめ度★★★★☆(05/6/4) |
||||||
|
||||||
 TFCについてはもはや説明もいらないだろうが、この「ジャド・フェアー」なる人物。名前は聞いたことがあるが音は聞いたことがなかった。70年代から「Half
Japanese」というバンドで活動。カルト的な人気を集めていた人物である。ちなみにジャドは多くの共作アルバムを出していて、ヨ・ラ・テンゴやパステルズらと競演している。どっちもヨレヨレさがいい感じの魅力を醸し出していそうだ。パステルズとの作品にはTFCも参加していて、その時からジャドとのつきあいが始まったらしい。 TFCについてはもはや説明もいらないだろうが、この「ジャド・フェアー」なる人物。名前は聞いたことがあるが音は聞いたことがなかった。70年代から「Half
Japanese」というバンドで活動。カルト的な人気を集めていた人物である。ちなみにジャドは多くの共作アルバムを出していて、ヨ・ラ・テンゴやパステルズらと競演している。どっちもヨレヨレさがいい感じの魅力を醸し出していそうだ。パステルズとの作品にはTFCも参加していて、その時からジャドとのつきあいが始まったらしい。作風としては、ジャドのディランとルー・リードを足して2でわったようなヴォーカルが、TFCのオーガニックなバックトラックと良く溶け合っていて、非常に面白い。TFCについてはメンバーがいつもとは違う楽器を演奏していたりと、リラックス、そして楽しみながら演奏している様子がうかがえる。曲もインプロヴァイズしながら作ったということで、いつものTFCサウンドに比べると、実験的な部分もあったりする。つまりいつもの完璧なメロディーやアンサンブルではなく、微妙にはずしているところがあるのだ。作り込んだところがないぶん、それがジャドの歌声に良くマッチしている。歌だけ聴けばシンプルで穏やかだ。 しかし、それだけでは終わらない。すごいなと思うのは詩人としてのジャドである。彼は歌詞を作るときに、その場ですらすらと言葉を出していくのだそうだ。つまり即興的に紡ぎ出していくのだ。しかしながら、決して適当なのではなく鋭い歌詞を書く。〈そして僕たちは闇雲に進む/ビートルズを引用すれば「派手にやれ」さ/ジョンを引用するなら「そうそう、その調子」/ポールならば「そう、うんそれでいい」/ジョージならば、ただの「そうだ」/リンゴならば「まあ、そんなもんかな」/ピート・ベストなら「何て言えばいいの?」/僕だったら「僕も何て言えばいいの?」〉(ピート・ベストはビートルズのデビュー前のドラマー。デビュー直前になってメンバーから解雇された)人生のビッグチャンスを逃した男。自分ではどうにもならないところで、道を曲げられてしまうこと。僕らなんて、はっきり言えばピート・ベストみたいなものだ。いやピート・ベストにさえなれやしないのが真実だろう。僕らはきっとどこかで人生を「つかみ損ねて」いる。少なくとも自分はそうだ。だからジャドのこの歌詞には胸を打たれる。 おすすめ度★★★☆(02/3/7) |
||||||
|
||||||
 「またこういう音か」という人もたくさんいるだろう。しかし、自分はやっぱりこういう音が好きだ。メロディーの美しさに重きを置き、乾いた叙情性を奏でるバンド。Thirteen
Sensesはその代表格とも言えるほど素晴らしい「招待状」を届けに来た。
「またこういう音か」という人もたくさんいるだろう。しかし、自分はやっぱりこういう音が好きだ。メロディーの美しさに重きを置き、乾いた叙情性を奏でるバンド。Thirteen
Sensesはその代表格とも言えるほど素晴らしい「招待状」を届けに来た。当然の事ながら、どの曲もグッド・メロディーである。ピアノのフィーチャー度が高いサウンドはトラヴィスやコールドプレイよりもKeaneを彷彿とさせるが、彼らのようにエモーショナルに自分の感情を表現するのではなく、あくまで押さえた形での表現がされている。そういう意味では、やはりコールドプレイに近いのだろう。つまりどんなにギターがメランコリックにかき鳴らされても、ファルセットヴォイスで唄われても、感情をこちら側に飛んでくることはない。あくまで彼らと聴き手の間をたゆたっている感じなのだ。 課題としてはもっともっとバンド自身の表現力の幅を広げるべきだと思う。アルバムの中でもう2,3違ったタイプの曲があれば、飽きの来ないアルバムになっただろう。残念ながら、アルバムの終わり頃には若干食傷気味になってしまうのだ。そこを打破するためにも、スタイルの拡張は必然的なものになるだろう。そしてその結果は次のアルバムに求められるだろう。例えば、Travisが「12memories」で挑戦したこと、Cpldplayのニュー・アルバムがこれまでとがらりとスタイルを変えているであろうということ。これらは表現者としては至極真っ当なアプローチである。そこで彼らが冒険を試みながらも、心の琴線に触れるような音楽をまた生み出せるのか。まだまだ見守っていく必要がある。 おすすめ度★★★★(05/3/9) |
||||||
|
||||||
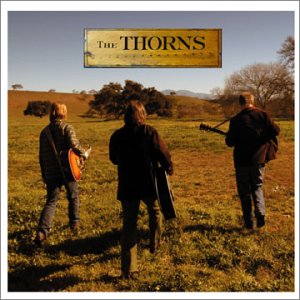 実は、これは興味本位で買った一枚。「マシュー・スウィート、ショーン・マリンズ、ピート・ドロージの三人による、CSN&Yのような絶妙のハーモニー・アルバム」という情報を聞きつけ、即購入。マシュー・スイートはすごく好きなのだが、「100%Fun」以降の作品があまりしっくりこなかった。というのは、マシューのメロディーセンスが微妙に霞がかかっている感じがしたからだ。最新作「キミがスキ・ライフ」に至っては、CCCDのため未聴である。ちょっと遠ざかりつつあるマシューであったが、今回もう一度「お近づきを」ということで聴いてみた。 実は、これは興味本位で買った一枚。「マシュー・スウィート、ショーン・マリンズ、ピート・ドロージの三人による、CSN&Yのような絶妙のハーモニー・アルバム」という情報を聞きつけ、即購入。マシュー・スイートはすごく好きなのだが、「100%Fun」以降の作品があまりしっくりこなかった。というのは、マシューのメロディーセンスが微妙に霞がかかっている感じがしたからだ。最新作「キミがスキ・ライフ」に至っては、CCCDのため未聴である。ちょっと遠ざかりつつあるマシューであったが、今回もう一度「お近づきを」ということで聴いてみた。1曲目「Runaway Feeling」から見事にやられた。ハーモニーが美しすぎる。2曲目「I Can't Remember」。もうノックアウトに近いです。メロディー切なすぎ。泣きすぎ。今回のアルバムでは3人で曲を作ったそうだが、主にメロディー作りはマシューが行ったらしい。この「I Can't Remember」、「100%Fun」収録の「Smog Moon」以来の泣きっぷりです。この後も、美しいメロディー、そして絶妙のコーラスがたっぷりとフィーチャーされた曲が続く。後半ちょっと飽きてしまうところもなくはないが、マシューファンとしては、彼の「泣きメロ」を充分堪能できます。かなりレトロチック(もろCSN&Yだし、バーズっぽさもある)な音ですが、こういうのも悪くありません。 おすすめ度★★★☆(03/8/9) |
||||||
|
||||||
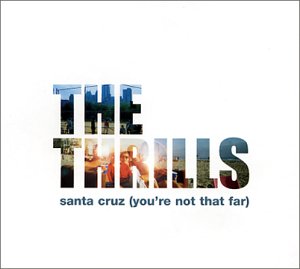 最近貪るように聴いているEP。スリルズはまだこのシングル一枚しか出していない。よって音源はまだ、この4曲しかないのだが、これだけでこのバンドが最高だと言うことがわかる。とにかく「santa
cruz」だけでも聴いて欲しい。ビーチボーイズのようなコーラスと極上のドリーミーなメロディーが見事に融合した曲である。ビーチボーイズの曲を聴いていると、メロディーの美しさの中にもろさが見え隠れしていて、「いつ終わってしまうかわからない」というカタルシスを感じてしまうことが多い。レディオヘッドのいくつかの曲にも同じような雰囲気を感じることがある。ビーチボーイズに影響を受けていると思われるバンドの中でも、これだけいいメロディーを書き、雰囲気までも体現しているバンドは本当に少ない。数多のブライアン・ウィルソン・フォロワーの中でもかなり質は高い。表題曲以外の曲も、捨て曲なし。キャッチーなものあり、胸が締め付けられるようなメロディーがあったりと、シングルなのにもうエンドレスで聴けてしまう。3月のアルバムが大変楽しみである。絶対聴いて欲しいバンド。 最近貪るように聴いているEP。スリルズはまだこのシングル一枚しか出していない。よって音源はまだ、この4曲しかないのだが、これだけでこのバンドが最高だと言うことがわかる。とにかく「santa
cruz」だけでも聴いて欲しい。ビーチボーイズのようなコーラスと極上のドリーミーなメロディーが見事に融合した曲である。ビーチボーイズの曲を聴いていると、メロディーの美しさの中にもろさが見え隠れしていて、「いつ終わってしまうかわからない」というカタルシスを感じてしまうことが多い。レディオヘッドのいくつかの曲にも同じような雰囲気を感じることがある。ビーチボーイズに影響を受けていると思われるバンドの中でも、これだけいいメロディーを書き、雰囲気までも体現しているバンドは本当に少ない。数多のブライアン・ウィルソン・フォロワーの中でもかなり質は高い。表題曲以外の曲も、捨て曲なし。キャッチーなものあり、胸が締め付けられるようなメロディーがあったりと、シングルなのにもうエンドレスで聴けてしまう。3月のアルバムが大変楽しみである。絶対聴いて欲しいバンド。おすすめ度★★★★★(02/2/11) So Much For The City 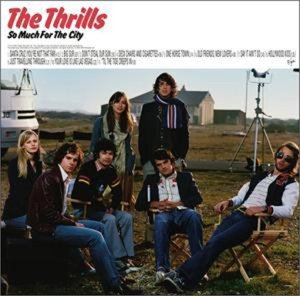 Thrillsというバンドに共感できる点は、アイルランドのブラックロックという日照時間の少ない土地から遙か離れたカリフォルニアをいつも夢見ているというところだ。実際バンドを解散するかしないかというところで、メンバーがカリフォルニアへと旅行をし、そこから強烈なインスパイアを得て今に至っているとのことである。僕も北海道の出身。夏は短く、海水浴などできない海がほとんどだ。ビーチボーイズやサザンではなく、鳥羽一郎がよく似合う海だ。thrillsと同じくらい太陽の光がさんさんと降り注ぐ土地や文化への憧れを持っている。これはきっとその土地に住んでみないとわからない感覚だと思う。傑作シングル「Santa
Cruz」も、そんな思いから産まれた曲ではないだろうか。ブライアン・ウィルソンも全くサーフィンができず、家の中に籠もって妄想と想像力だけでビーチボーイズの傑作を次々と生み出したのは有名な話であるが、「憧れ」と「想像力」というのは作品を作る上ですごい力を発揮するのだなと改めて思う。 Thrillsというバンドに共感できる点は、アイルランドのブラックロックという日照時間の少ない土地から遙か離れたカリフォルニアをいつも夢見ているというところだ。実際バンドを解散するかしないかというところで、メンバーがカリフォルニアへと旅行をし、そこから強烈なインスパイアを得て今に至っているとのことである。僕も北海道の出身。夏は短く、海水浴などできない海がほとんどだ。ビーチボーイズやサザンではなく、鳥羽一郎がよく似合う海だ。thrillsと同じくらい太陽の光がさんさんと降り注ぐ土地や文化への憧れを持っている。これはきっとその土地に住んでみないとわからない感覚だと思う。傑作シングル「Santa
Cruz」も、そんな思いから産まれた曲ではないだろうか。ブライアン・ウィルソンも全くサーフィンができず、家の中に籠もって妄想と想像力だけでビーチボーイズの傑作を次々と生み出したのは有名な話であるが、「憧れ」と「想像力」というのは作品を作る上ですごい力を発揮するのだなと改めて思う。今回のアルバムも、これまでのシングル同様、クオリティの高い曲が並んでいる。60〜70年代のウェストコーストサウンドとでもいうのだろうか、爽やかなメロディーとコーラスを基調としながらも時々叙情的な所も聴かせ、なかなかつぼを押さえている。全体を通すと、若干一本調子に感じられるところもあるが、デビューアルバムとしては素晴らしいと思う。現実逃避でビーチに行きたい人には是非お勧めする。 おすすめ度★★★★☆(03/8/5)
|
||||||
|
||||||
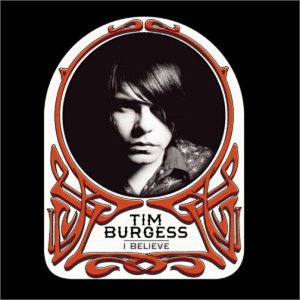 シャーラタンズがここのところきつい状況にあるのではないかと思っていたのは、最新作の「Wonderland」が、あまりにもファンキーでグラマラスな路線を行ったばかりに、本来のスリリングなグルーヴが失われてしまったからである。いい作品なのだろうが、シャーラタンズがやるロックではないなと強く感じた。このソロ作品を聞くと、あの路線はかなりティムの趣味であるということが実感できる。というくらい、このソロ作品は自由でファンキーでポップな作品である。1曲目からファルセット全開のファンクナンバー。ずっと、こんな感じだときついなと思っていたのだが、この後は実にいろいろな展開を見せてくれる。フォークっぽいのもあれば壮大なバラードも。シャーラタンズよりも軽い分、ポップなメロディーが引き立てられている。ティムがやってみたいと思っていたものが、このアルバムにぎっしりと詰まっている。こういうものが聞きたい、というのがはっきりしない気分の時は、ぜひおすすめしたくなる。シャーラタンズファンでなくても楽しめる一枚。 シャーラタンズがここのところきつい状況にあるのではないかと思っていたのは、最新作の「Wonderland」が、あまりにもファンキーでグラマラスな路線を行ったばかりに、本来のスリリングなグルーヴが失われてしまったからである。いい作品なのだろうが、シャーラタンズがやるロックではないなと強く感じた。このソロ作品を聞くと、あの路線はかなりティムの趣味であるということが実感できる。というくらい、このソロ作品は自由でファンキーでポップな作品である。1曲目からファルセット全開のファンクナンバー。ずっと、こんな感じだときついなと思っていたのだが、この後は実にいろいろな展開を見せてくれる。フォークっぽいのもあれば壮大なバラードも。シャーラタンズよりも軽い分、ポップなメロディーが引き立てられている。ティムがやってみたいと思っていたものが、このアルバムにぎっしりと詰まっている。こういうものが聞きたい、というのがはっきりしない気分の時は、ぜひおすすめしたくなる。シャーラタンズファンでなくても楽しめる一枚。おすすめ度★★★☆(03/12/2) |
||||||
|
||||||
 「加爾基・精液・栗ノ花」を作ったときには、やっぱりすごいもん作ったなということと同時に、ある種の「手詰まり感」も感じた。これから一自作自演屋として、どう「椎名林檎」を表現していくのか僕としては全く見えなかったし、その先へ進んでいくような高揚感も感じることは出来なかった。 「加爾基・精液・栗ノ花」を作ったときには、やっぱりすごいもん作ったなということと同時に、ある種の「手詰まり感」も感じた。これから一自作自演屋として、どう「椎名林檎」を表現していくのか僕としては全く見えなかったし、その先へ進んでいくような高揚感も感じることは出来なかった。彼女はこれまでも、オリジナルアルバム以外にも「絶頂集」「唄ひ手冥利」のような企画的アルバムを出しているが、僕にはそれらの作品がどうにも「ガス抜き」のようにしか見えなかったたちで、実際は違うのかもしれないけど、やはりこれだけ濃密なものを作り続けるためにはこういう作業も必要なのだろうと考えていた。 しかしながら、この東京事変は彼女の中でそういう位置づけではないだろう。まず驚くのが、各メンバーのプレイヤビリティーあふれる演奏だ。特に1曲目から「遭難」までの流れは、猥雑でしなやかなグルーヴを描いている。一ロックバンドとしてとてもかっこいい。勢いがあって、ラフながらもアンサンブルとしてしっかり決まる、これがこのバンドの強みだろう。椎名林檎のバックバンドではなく、各プレイヤーの「顔」が見える演奏である。椎名林檎の所信表明のために作られたバンドだというのに不思議であるが、まぁ、変な話椎名林檎の負担は軽くなったのではないだろうか。これだけ生き生きした林檎嬢を見るのは久しぶりであるような気がする。まだ「新境地」といえるほどの世界観は提示できていないと思うが、東京事変としての音楽はこれでいいのだろう。ソロでの緊張感あふれる感じも捨てがたいのだが、この肉体的なグルーヴは大きな武器だ。 おすすめ度★★★☆(05/1/5) |
||||||
|
||||||
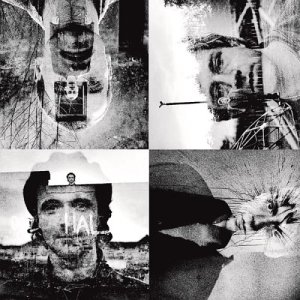 「The Man
Who」でのブレイクが決定打となり、Travisは美しいメロディーを、ガラス細工のような繊細なアレンジで奏でる作品を作るバンドとなった。「Good
Feeling」が結構好きであった人間にとっては、驚くようなシフトチェンジであったが、今では「The Man
Who」以降の彼らこそが本来の姿であるのだと素直に認めることができる。近頃グッドメロディーが少なくなってきたと感じる中で、破格の名曲群をドロップしてきたということに、もう何も文句はつけられない。当然今作もこれまでのような展開でくるのかと思っていたが、ちょっと違うようである。 「The Man
Who」でのブレイクが決定打となり、Travisは美しいメロディーを、ガラス細工のような繊細なアレンジで奏でる作品を作るバンドとなった。「Good
Feeling」が結構好きであった人間にとっては、驚くようなシフトチェンジであったが、今では「The Man
Who」以降の彼らこそが本来の姿であるのだと素直に認めることができる。近頃グッドメロディーが少なくなってきたと感じる中で、破格の名曲群をドロップしてきたということに、もう何も文句はつけられない。当然今作もこれまでのような展開でくるのかと思っていたが、ちょっと違うようである。1曲目「Quicksand」は、力強いピアノから始まるが、これまでの繊細な作りとは違って美メロながらずいぶん骨太な印象を受ける。明らかにトラヴィス節ながら、無骨な感じだ。2曲目「Beautiful Occupation」も同様な印象を受ける。尤もこの曲はイラク戦争における理不尽な行為を歌った曲。プロテストソングと言っても過言ではない。これまでのトラヴィスであれば、汚れた世界に美しい花を敷き詰めていくアプローチであったが、今作は汚れた世界の根本を見つめ、そこに一つ一つ美しい花の咲く種をまいているような感じなのだ。よって、同じ美しい音楽ながら、感じ方がすごく違う。今作では奥の深さがすごく感じられるのだ。セルフ・プロデュースの影響もあると思うが、トラヴィスは新たな扉を開けたように思う ただ、好みとしては評価が分かれるところだと思う。僕は結構好きだけど「The Man Who」と比べるとどうかなぁ。今回も1番好きなのは「Re-Offender」だったりするし。この曲は「これぞ、トラヴィス」って感じの曲です。 おすすめ度★★★☆(03/11/30) |
||||||
| Ode To J.Smith |
|
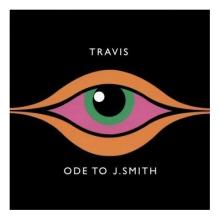 Travis6枚目のアルバムは、自主レーベルRed Phone
Boxからのリリース。環境が変わったからなのか、前作からのインターバルも短く、サウンドプロダクションもこれまでと大きく変わっている。 Travis6枚目のアルバムは、自主レーベルRed Phone
Boxからのリリース。環境が変わったからなのか、前作からのインターバルも短く、サウンドプロダクションもこれまでと大きく変わっている。 オープニングである「Chinese Blues
」から、腹にズシッと来るドラム、重々しいギターリフで、これだけ聴いたら絶対誰もTravisだとは思わないだろう。メロディーラインはややメランコリックな線を残しながらも、硬派な1曲に仕上がっている。そして、2曲目「J.
Smith 」ではクラシカルな野太い男性コーラスまで入るという、男臭いというか意図的に重く仕上げようとするねらいが感じられる。そして、3曲目「Something
Anything
」は、これまたやや乱暴なギターリフで、メロディーはかなり面影があるものの、これまた感傷に浸るような余地なくタイトに仕上がっている。 従来のTravisが好きだという人は6曲目「Last Words」からやっと安心できる。これはまさに「Travis印」とも言えるメランコリアが爆発する1曲、次の 「Quite Free 」もこれまでの彼らから全く違和感がない、アコースティックな温もりを持った1曲だ。また、ボーナストラックの「サラ」もピアノだけのシンプルな演奏ながら心にしみる。 というように、ガラリと印象を変えた曲と、ステレオタイプな曲とがこのアルバムには混在している。個人的にどちらが好きかと聞かれたら、やはり従来のタイプが好きと答えるだろう。 それはつまり、これまで彼らが生み出してきた作品が抜群のクオリティーを誇っているからだ。極上のメランコリア、繊細なアレンジ。傑作「The Man Who」から「叙情派ロック」みたいな言葉が生まれるほど、Travisはその道のど真ん中を歩いてきた。そしてまた、その後を通れるバンドもいなかったと思う。数多のフォロワーを生み出しながら、彼らに追随できるほどの力を持ったバンドはそうはいないだろう。 それだけ今までの作品が自分にとってインパクトがあるだけに、アルバムをトータルで見るとまだやっぱり馴染んではこないのが正直な感想。それでも、このバンドに対する自分の信頼は微塵も揺らがないが。 おすすめ度★★★☆(10/08/08) J.Smith |
|
|
||||||
|
彼らが叩きつけるのは、近年とくとお目にかかれなかった正統派ブリティッシュロック。さすがはリヴァプール。 タイトなビートにポジティヴなメロディー。小細工は一切ナシで、「素材で勝負」みたいな。このサウンドを聴いて、誰もが思い浮かべるのが、The La'sであろう。サマソニで登場したときは姿格好までThe La'sであった。 とにかくここまで徹頭徹尾グッドメロディーにこだわって作られた作品は、なかなかないだろう。それは、思えば60年代のUKバンドにとっては当たり前のことであったはずだ。ビートルズ、ストーンズ、ホリーズ、ハーマンズ・ハーミッツ、キンクスといった名だたるバンドはみんなメロディーで勝負してきた。強いて言えば、僕はメロディーこそが音楽を構成する要素で一番強い魔法をかけられるものだと思っている。メロディー至上主義かもしれない。そして、Troubadoursのフロントマンであり、ソングライターでもあるマーク・フリスもきっとメロディーに対するこだわりは尋常ではないと思う。目新しさや斬新なアイディアはないが、メロディーの完成度は実に高水準。先人の教えを忠実に守っていくことがむしろ彼らの使命のようにも思える。 「名曲」揃いなのは間違いないが、惜しむらくは「超名曲」と思わせるようなものが1曲ほしかったこと。そうなればアルバムの流れがもっと豊かになったと思う。それでも、リヴァプール好きな人、最近のUKロックはなんだか小難しいなと思っている人は絶対に聴いてほしい。 おすすめ度★★★★(10/09/08) |
||||||
|
||||||
 The
Musicと同時期に購入した一枚であるが、個人的には断然こちらの方が好きである。アルバムが出る前からかなり話題になっていたバンドであるが、シングルはかっこいいなと思いつつも、すごくはまるというところまでは行かなかった。フジロックでは遠くで聴いたのだが、いわゆるブルースを基調にしたという感じはしなく、バリバリのガレージ系の音に聞こえた。僕は実をいうとあんまりブルース系は得意ではなく、ホワイト・ストライプスはなんとかいけるものの、ジョンスペも最後まで聴けなかったりする。そういう意味では嬉しい誤算で、このアルバムも見事にフジロックでの雰囲気を継承したものとなっている。 The
Musicと同時期に購入した一枚であるが、個人的には断然こちらの方が好きである。アルバムが出る前からかなり話題になっていたバンドであるが、シングルはかっこいいなと思いつつも、すごくはまるというところまでは行かなかった。フジロックでは遠くで聴いたのだが、いわゆるブルースを基調にしたという感じはしなく、バリバリのガレージ系の音に聞こえた。僕は実をいうとあんまりブルース系は得意ではなく、ホワイト・ストライプスはなんとかいけるものの、ジョンスペも最後まで聴けなかったりする。そういう意味では嬉しい誤算で、このアルバムも見事にフジロックでの雰囲気を継承したものとなっている。とはいえ、いわゆる今のガレージ系というものはすべからくブルースの奔放なところとロックのグルーヴの融合が感じられるわけで、22−20Sはとりわけそのブルース的要素がよりわかりやすい形で出ているということは間違いないだろう。それでも僕のような人間がすんなり聴けてしまうのは、3ピースバンド特有の演奏の緊張感が漲っているからだろう。1曲目、ドラムの音が聞こえた瞬間からそれは分かる。また、1曲1曲がコンパクトにまとめられているところもいい。結果、このバンドの勢い、ライヴでの雰囲気がアルバムにすごく反映されていると思う。この先Gomezのようにならないことを祈っています。 おすすめ度★★★★☆(04/11/6) |
||||||
|
||||||
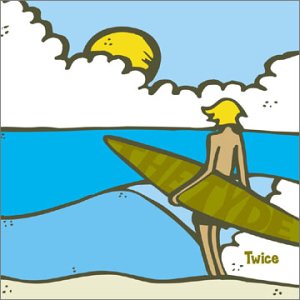 「ヴェルヴェット・クラッシュのリック・メンクが正式加入した、バーズ直系のキラメキギター・ポップ」ということで、バーズ直系にたまらなく弱い僕としては、ついつい興味のわく一枚。1曲目はもろバーズであるが、2曲目以降はアップテンポな感じが続き、そこにジャングリーなギターがコーティングされてある。フェルトあたりが引き合いに出されているが、僕はオレンジ・ジュースのような80年代のネオアコのテイストを感じた。あの「キラメキ感」が、このアルバムには詰まっている。また、自分が高校生の頃にアズテック・カメラやフリッパーズに心躍らされていた頃のことを思い出す。昂揚感と甘酸っぱさが暴走している感じ。アルバム後半はやや抑えられて、彼ら十八番のサイケデリックなテイストが顔を出してくるが全体の印象としてはかなりポップだと思う。そういうわけで、このアルバムは、今年の夏のドライブBGMとして何度となく聴いた。ジャケットも中身もかわいい一枚。 「ヴェルヴェット・クラッシュのリック・メンクが正式加入した、バーズ直系のキラメキギター・ポップ」ということで、バーズ直系にたまらなく弱い僕としては、ついつい興味のわく一枚。1曲目はもろバーズであるが、2曲目以降はアップテンポな感じが続き、そこにジャングリーなギターがコーティングされてある。フェルトあたりが引き合いに出されているが、僕はオレンジ・ジュースのような80年代のネオアコのテイストを感じた。あの「キラメキ感」が、このアルバムには詰まっている。また、自分が高校生の頃にアズテック・カメラやフリッパーズに心躍らされていた頃のことを思い出す。昂揚感と甘酸っぱさが暴走している感じ。アルバム後半はやや抑えられて、彼ら十八番のサイケデリックなテイストが顔を出してくるが全体の印象としてはかなりポップだと思う。そういうわけで、このアルバムは、今年の夏のドライブBGMとして何度となく聴いた。ジャケットも中身もかわいい一枚。おすすめ度★★★★(03/9/10) |
||||||
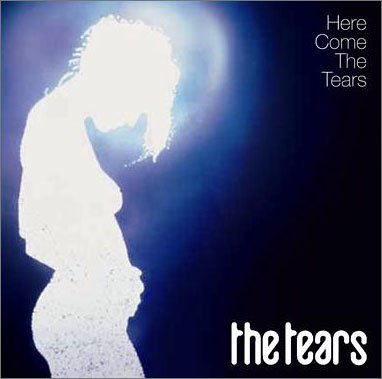 ブレット・アンダーソンとバーナード・バトラーが再び手を組んで立ち上げたバンド、The Tearsのデビューアルバム。このふたりはもちろんブリット・ポップ全盛のUKで強烈な個性を放っていたバンドSuedeの元メンバー。僕は2ndまではよく聴いていた。そしてそれはバーナードが脱退するまでのSuedeということで、僕はブレットのヴォーカルよりもバーナードの猥雑なギターが好きだった。
ブレット・アンダーソンとバーナード・バトラーが再び手を組んで立ち上げたバンド、The Tearsのデビューアルバム。このふたりはもちろんブリット・ポップ全盛のUKで強烈な個性を放っていたバンドSuedeの元メンバー。僕は2ndまではよく聴いていた。そしてそれはバーナードが脱退するまでのSuedeということで、僕はブレットのヴォーカルよりもバーナードの猥雑なギターが好きだった。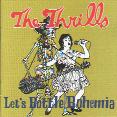 このバンドは率直に言って2nd以降は急速に尻つぼみになりそうな予感がしていたが、まさに嬉しい誤算だ。1st,「So Much For The
City」は、真夏の青い海とサーフィンの文化に恋焦がれるものの胸の内を代弁した素晴らしいアルバムであった。「Santa
cruz」の冒頭のフレーズ「なぁ、教えてくれよ。どこで全てがおかしくなったのか」。どことなく、冴えない男が海岸沿いをぶらぶらしている姿が目に浮かぶ。それだけの情景描写力のあるサウンドは、メンバーの音楽的リスペクトと知識量が見事に反映されていて、デビューとしては完璧なものであった。そうなるときつくなるのが次の作品で、前作の印象が強いだけに、似たようなものを作ってしまうと、インパクトに欠ける。思い切って音楽的に冒険したいところだが、彼らには少々似合わない。さて、どうするか。
このバンドは率直に言って2nd以降は急速に尻つぼみになりそうな予感がしていたが、まさに嬉しい誤算だ。1st,「So Much For The
City」は、真夏の青い海とサーフィンの文化に恋焦がれるものの胸の内を代弁した素晴らしいアルバムであった。「Santa
cruz」の冒頭のフレーズ「なぁ、教えてくれよ。どこで全てがおかしくなったのか」。どことなく、冴えない男が海岸沿いをぶらぶらしている姿が目に浮かぶ。それだけの情景描写力のあるサウンドは、メンバーの音楽的リスペクトと知識量が見事に反映されていて、デビューとしては完璧なものであった。そうなるときつくなるのが次の作品で、前作の印象が強いだけに、似たようなものを作ってしまうと、インパクトに欠ける。思い切って音楽的に冒険したいところだが、彼らには少々似合わない。さて、どうするか。